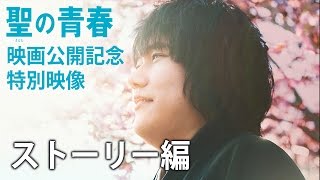かるび(@karub_imalive)です。
10年ぶりとなる、デスノートの実写映画の新作続編「DEATH NOTE デスノート Light up the NEW World」(以下、デスノートLNWと記載)を見てきました。2015年以降、TVドラマや演劇で再度取り上げられ、そしてこの秋リリースされた新作が、デスノートの10年後を描いた後日譚となります。

早速初日に気合を入れてみてきましたので、以下感想を書いてみたいと思います。
※後半部分は、ネタバレ部分を含みますので、何卒ご容赦下さい。
- 1.映画の基本情報
- 2.主要登場人物とキャスト
- 3.あらすじ(ネタバレ無し)
- 4.映画を楽しむための見どころ(ネタバレ無し)
- 5.あらすじ(※ネタバレ有注意)
- 6.伏線や設定などの解説(※ネタバレ有注意)
- 7.原作マンガとの設定相違点(※ネタバレ有注意)
- 8.ノベライズ版との設定相違点(※ネタバレ有注意)
- 9.感想とまとめ
- 10.映画を楽しむための小説やガイドなど(随時追加)
1.映画の基本情報
【監督】佐藤信介(「図書館戦争」「アイアムアヒーロー」他)
【脚本】真野勝成(「ST 赤と白の捜査ファイル」「刑事7人」他)
【原作】大場つぐみ・小畑健(「バクマン」「プラチナエンド」)
2.主要登場人物とキャスト

すでにTVやネット等で流れている予告編にてクローズアップされている通り、今作の主役は、三島、竜崎、紫苑です。個性もバックグラウンドも違う3人の天才達がデスノートを巡って攻防を繰り広げます。
三島創(東出昌大)
デスノート対策本部特別チーム捜査官。署内No.1のキラ研究家である。
竜崎(池松壮亮)
新生キラ事件に対応するため、ICPOから派遣された探偵。Lの後継者。
紫苑優輝(菅田将暉)
狂信的なキラ信奉者にして、天才的なサイバーテロリスト。
弥海砂(戸田恵梨香)
夜神月の彼女で、女優。元デスノート保有者。
七瀬聖(藤井美菜)
デスノート対策本部特別チーム捜査官。三島の片腕的存在。
青井さくら(川栄李奈)
デスノート所有者。無職の20歳。
御厨賢一(船越英一郎)
デスノート所有者。最高裁判事。
3.あらすじ(ネタバレ無し)
ノートに名前を書かれた人間は必ず死ぬという、「デスノート」を操り、世の中を震撼させた夜神月、通称キラによる大量殺人事件と名探偵”L”の活躍から10年。世界には再び原因不明の突然死事件が頻発するようになっていた。地上に落とされた新たな6冊のノートの存在が判明し、日本のデスノート対策本部に、新生キラからのメッセージが届く。キラ事件を熱心に追い、熱心に捜査を行う三島を筆頭に、新たにICPOから事件解決に向けて送り込まれた竜崎が、事件の解決に向けて動き出す。
新生キラとは誰なのか、そして、三島と竜崎はキラによる大量殺人事件を再び解決することができるのか?地上に新たに落とされた6冊のデスノートをめぐり、キラと竜崎たちの戦いが再び切って落とされた!
4.映画を楽しむための見どころ(ネタバレ無し)
4-1.デスノートのルールを覚えておくとより楽しめる!

この映画は、一応マンガ原作や、2006年の実写版「デスノート」を見ていなくても最低限楽しめるように配慮はされていますが、前提としてデスノートについての前提知識は入れておいたほうが良いと思います。
デスノートには数え切れないほどのルールがありますが、今映画作品で覚えておいたほうが良いルールは、以下のとおりです。(当たり前の項目は省略)
・デスノートは書く人物の顔が頭に入っていないと効果は得られない。同姓同名の人物は死ぬことはない。
・名前のあとに死因を書かなければ、全て心臓麻痺となる。
・デスノートに触ったものだけが、死神を見ることができる。(切れ端でも可)
・デスノートの所有権を放棄したら、デスノートに関する記憶をすべて失う。デスノートの一部にでも触れれば、記憶はまた蘇る。(保持するには所有権を持たなければならない)
・デスノートに一度書かれた人間の死は変更することができない。
・デスノートには、最大23日間の先日付まで死亡日付を指定することができる。
・人間界に一度に存在できるデスノートの上限は6冊。7冊目は無効になる。
・デスノートは破って切れ端に書いても、効果を得ることができる。
・死神が自分のデスノートに任意の人間の名前を書くと、その死神は死ぬ。
4-2.誰が新生「キラ」なのか
映画中、最終場面ではキラが判明します。でも、とにかく手がかりが少ないことと、展開にスピード感があるので、物語のスジを追いつつ、推理するのは意外に難易度が高いかもしれません。
4-3.なつかしい前作での出演者たち
2006年の映画2部作「DEATH NOTE」「DEATH NOTE the LAST NAME」で活躍した夜神月(藤原竜也)、L(松山ケンイチ)、弥海砂(戸田恵梨香)、松田桃太が今作でも出演しています。特に夜神月を失い、大人になった弥海砂が見せる寂しそうな表情が印象的でした。
スポンサーリンク
5.あらすじ(※ネタバレ有注意)
夜神月とLが死闘を繰り広げたキラ事件から10年。死神大王の命により、キラの後継者を探しだすため、6冊のデスノートが、新たに下界へと落ちていった。
ロシアの雪深い街で、医師のアレクセイがそのうちの1冊を拾う。「楽になりたい」と訴える寝たきりのヴァシリィの名前を半信半疑でノートに書くと、間もなくヴァシリィは死亡した。まもなく、アレクセイは同じような安楽死希望者をノートに書きまくる毎日となる。
同じ頃、日本でも渋谷で大量無差別殺人事件が起きていた。デスノートによる犯罪を疑ったデスノート対策本部の三島創は、チームとともに現場へ急行。パニックとなった現場の状況から、「死神の目」を持つ、青井さくらという20歳の女性が浮上。
三島が逮捕に踏み切る直前、ICPOから探偵Lの後継者として捜査に加わっていた竜崎が麻酔銃で青井さくらを狙撃。青井は倒れたが、すでに心臓麻痺で死んでいた。白いコートを来た謎の男(紫苑)がデスノートで殺したのだった。
押収したデスノートを持ち帰り、対策を話し合うチームメンバー。竜崎に促されてデスノートに触れると、「ベポ」という死神が現れた。ベポに尋問する竜崎。ベポによると、人間界には現在6冊のデスノートが存在し、7冊目が人間界に仮に持ち込まれても無効になるという。これを受け、デスノート対策本部では、現存する6冊全てを確保して、事件の収束を狙う戦略を立てた。
その日、世界中のパソコンやスマホが一斉にキラ=夜神月の動画を配信する通称「キラウイルス」に感染する。
僕が、キラだ。
僕は人の死を自由に操ることができる。
僕は、悪意と、憎悪に満ちたこの世を浄化し、キラが平和な新世界へと導く。
僕が、キラだ。
キラウイルスの真の目的は、感染した端末から個人情報を抜き取ること。対策本部の所属員は、みな家族のいない人間で構成され、松田桃太(10年前のキラ事件の唯一の経験者)以外は、みな偽名で通していた。
10年前、夜神月と共犯関係だった弥海砂は、デスノートの所有権を放棄した際に、ノートに関する全ての記憶を失っており、証拠不十分で釈放され、現在は女優として大成功していた。また、弥海砂を担当していた検事、魅上は1年前から失踪中。
弥海砂は、楽屋で届けられたプレゼントの中からデスノートを取り出し、ノートに触れた瞬間に過去の記憶を全て思い出した。キラの使者を自称する紫苑優輝が現れ、海砂に10年前、夜神月から聞いた「約束の地」を教えて欲しいと頼み込む。
竜崎もまた、密かにデスノート保持者だった。自宅を出る時に所有権を放棄し、帰宅すると所有権を戻すという特殊な処理をすることで、デスノート保持者から、自分がノートの所有者であることを隠すことができる。ノートの死神は、アーマという雌の死神だった。

ある日、キラ信奉者であるキャスター、貴世河春奈が、レストランで食事中に突然死亡した。殺したのは、最高裁判事、御厨賢一。キラの信者と信奉者に対して激しい憤りから、片っ端からデスノートで殺していた。
御厨が執務室でデスノートを広げていた時、ちょうど宅急便の配達員に扮した紫苑が訪ねてきて、その場で御厨をデスノートで操り、御厨のデスノートを奪っていくのであった。御厨はデスノートの記述通り、警視庁内で武器を持って「Lの後継者に告ぐ。キラはすでに3人の所有者を処刑した。これより、4人目の処刑を行う」と叫んだ後、自殺して果てた。
紫苑優輝は、熱心なキラの信奉者。家族全員を異常者に殺され、毎日怯えて暮らしていた中、キラがその異常者を排除してくれたことがきっかけである。紫苑は、世界中に散らばるデスノートを収集していた。
ある日、紫苑は、デスノートの収集に邪魔となるLの後継者に向かってTVで声明文を出すと、竜崎は死亡した「L」のCGに暗号文メッセージを入れて返答する。
これをきっかけに、竜崎と紫苑はチャット経由で直接オンライン上でコンタクトを取るようになる。コンタクト中に紫苑の住所を逆探知した三島達は、都内のアジトへと踏み込む。しかし、それは紫苑が仕掛けた巧妙なワナであり、現場はもぬけの殻だった。代わりに、「松田桃太、笑顔で自殺する」と書かれたデスノートが残されており、松田は拳銃自殺するのだった。

この捜査失敗をきっかけに、捜査一課の須賀原の命令により、デスノート対策本部は解散となる。三島と竜崎は言い争いをして、竜崎は、このあと一人で捜査を進めると言い残し、立ち去ってしまう。残された三島は、一人対策本部に残り、竜崎が紫苑へと当てた暗号化された返答メッセージを解読してみると、竜崎が最後の1冊を持っていることを示唆する文面がそこに書かれていた。

竜崎が帰宅すると、三島が拳銃を構えていた。しかし、竜崎のノートは、白紙のままだった。竜崎は死んだLとの約束でデスノートは使わないと心に誓っていた。(※映画版「デスノート」(2006)では、Lは夜神月を仕留めるため自分で自分の名前をノートに書き込んでいた)
三島が竜崎の家を出ようとすると、三島は竜崎宅で捜査一課が重要参考人として連行されることに。過去の魅上検事失踪事件の報告漏れを咎められ、留置所に入れられる三島。留置所へ入ってきた竜崎は、三島を出して、警視庁内で保管しているノートと自らのノートを持って紫苑をおびき出し、逮捕を試みることにしたのだ。
三島は、対策本部にて竜崎を後方支援する。三島のチームメイト3人も加わり、紫苑とまず13時に東大川門駅で待ち合わせて、ロッカーでノートの切れ端を交換しあい、本物であることを確認してから、14時30分に東京ニューシティーホールで顔を合わせることに。
三島は、警察官を配置し万全の体制で臨むも、キラウイルスによりダウンさせられる警視庁のサーバー。なんとか回復するも、十分な支援ができないまま、竜崎は現場に現れた弥海砂と対面していた。

直前に、再び「死神の目」を契約した弥海砂は、見えた竜崎の本名をノートに書くと、竜崎はその場に倒れた。現場に向かった黒本、浦上も弥海砂に殺されてしまう。
「死神の目」で夜神月の写真を見て、夜神月がもはや生存していないことを悟ると、弥海砂は、紫苑に後を託すため、夜神月との約束の場所を「甲羅山山頂のホテル、最上階」と紫苑に教え、自らの名をデスノートに書いて死亡した。
甲羅山山頂のホテルで、キラの後継者を待つ紫苑。夜神月が存命でないことが確定的になった今、リュークと死神の目の契約をしてキラの後継者を殺そうというのだ。
そこへ、顔を隠して踏み込んできた三島。銃を構えている。さらに、竜崎も入ってきた。紫苑は、すかさず「俺がキラだ」と仮面を外して叫ぶ竜崎の本名を手元のノートに書き込んだが、竜崎は倒れない。ノートも本物だ。
つまり、10年前と同じく、竜崎の名前はすでに他のデスノートに書かれているということだった。キラは三島であると断定する竜崎。所有権を放棄していたため記憶を失っていたのだ。
その場でデスノートを改めて手にした三島は、記憶を取り戻した。アメリカで秘密裏に誕生していた夜神月の子供とその後見人魅上は、1年前からキラとしての活動を始めていたが、疑心暗鬼にかられた魅上は、夜神月の子供をデスノートで殺してしまう。三島は、魅上と銃撃戦になり魅上を殺すと、デスノートを回収し、新生キラとして生きることに決めた。
三島は、リューク経由で紫苑を発見し、紫苑を操ることに成功。そして、対策本部に竜崎が現れた時、死神の目を契約した三島は、怪しまれないよう、竜崎の本名を先日付(12月25日)でデスノートに書き込み、その直後にノートの所有権を放棄することで、一切の記憶を失っていたのだった。
放心状態の三島に対して、夜神月にならい、腕時計に仕込んだデスノートで三島を仕留めようとする紫苑。と、そこに須加原の部隊が到着し、ヘリコプターから3人を機銃掃射した。応戦するも、紫苑は機銃掃射を受け、死亡。
三島と竜崎は秘密のトンネルから何とか脱出したが、そこへ無線で一切の情況を聞いていた七瀬が入ってきた。兄をキラに殺された憎しみから、三島を殺そうとする七瀬。

しかし、その瞬間、アーマが七瀬の名前をデスノートに書き込み、七瀬が倒れていた。砂になって消えていくアーマ。
事件後、一旦は日本政府の下に揃った6冊のデスノートのうち、4冊が強奪され、捜査が再開される。三島は投獄されたが、竜崎が死ぬ直前、超法規的措置で三島と入れ替わった。死んでゆく竜崎にかわり、三島が新たな竜崎となって、デスノートを取り返す捜査を続けるのだった。
エンディング、エンドロールが終わった後、流れるキラの動画ファイル。
「・・・計画通りだ。」
スポンサーリンク
6.伏線や設定などの解説(※ネタバレ有注意)
6-1.竜崎とLの関係はどうなっているの?
Lのように天才的な頭脳を持つ竜崎は、Lの子供ではなく、「Lの遺伝子を受け継いだ存在」と説明されています。(子供だったら年齢が合わないですし)映画中で、何度かせきこみ、自宅で薬を飲むシーンや、髪の毛の色がところどころ白くなっているあたりは、遺伝子操作の副作用なのかもしれません。
6-2.死神の目とは何なのか?
デスノート保有者は、死神と「死神の目」を契約することで、目視しただけで人の名前と年齢がわかるようになります。その場で見えた名前をノートに書き込むことで、より効率的に殺せるようになるメリットがありますが、そのかわり契約者の余命の半分を死神に渡すことになります。
今作では、結局、三島、紫苑、弥海砂、そして青井さくらが目の契約をしていました。原作や映画1作目より随分みんな大胆になっていますね・・・
6-3.デスノート対策本部はなぜ解散したのか
直前に紫苑のアジトへ踏み込んだ松田桃太は、キラウィルスにより警視庁のサーバから個人情報を抜かれており、紫苑によりデスノートで凄惨な殺され方をしました。捜査一課からデスノート対策本部にも出入りしていた須賀原もまた、本名で活動していました。
映画中での反応から、須賀原はこの一連の事件を見て怖くなったため、松田の変死と突入失敗を機に、強引に対策本部を解散したものと思われます。また、映画冒頭から、須賀原だけデスノートの存在や取扱について、ついていけていない雰囲気も出していましたよね。
6-4.弥海砂と「約束の地」について
紫苑からデスノートを返却された弥海砂は、楽屋でデスノートに触れてから、過去の記憶を取り戻した際に、夜神月から聞いていた「約束の地」も思い出したのでしょう。
車中で最初に紫苑と対面した際に教えなかったのは、その直前にキラウィルスを目にして、もしかしたら夜神月が生きているかもしれないと考え、自分自身が「約束の地」へ行く希望を見出していたからと推測します。
しかし、リュークと死神の目を契約し、夜神月の写真を見た時、夜神月が死亡していることを確認し、最終的にその後継者を目指す紫苑に「約束の地」を教えました。弥海砂にとって、新世界を創ることなどには興味はなく、夜神月が全てだったのでしょう。
6-5.夜神月の子供と魅上について
夜神月は、死ぬ前にアメリカで自分の子供を設け、リュークに依頼し、子供にデスノートを託しました。(どうやって、なぜ・・・等は映画内では説明なし)月へ心酔していた魅上は、子供の後見人を務めていましたが、夜神月Jrが成長するにつれ、疑心暗鬼にかられ、魅上は夜神月Jrをデスノートで殺してしまいます。
その現場に居合わせた三島は、恐怖感から魅上を射殺し、デスノートを手に入れて新生キラになったのでした。
6-6.誰がキラなのか推理が可能な伏線はあったのか?
この映画でのキラは、三島でした。
ただし、三島=キラである、ということを状況証拠や演者の表情から読み取ることのできるシーンは極端に少なかったと思います。
映画中盤で、竜崎邸を出ようとした三島が重要参考人として拘束され、警視庁サーバを調査した須賀原から「魅上事件の報告漏れ」を突っ込まれたことが唯一と言って良い伏線でした。映画の冒頭では、すでにデスノートの所有権を放棄した状態で始まっているので、三島の言動からは少なくとも「キラ」であるという証拠は見つかりにくい状態でした。
青井さくら死亡後、押収したデスノートを触り、ベポを尋問するシーンで記憶が戻らなかったのは、ベポのデスノートは過去に三島が使用した履歴がないからです。記憶が戻る条件は、触ったデスノートの所有権を過去に一度でも持つ必要があります。
6-7.なぜデスノートは6冊に増えたのか
人間界で存在できる上限、6冊までデスノートが増えたのは、死神大王からの「夜神月に続くキラ候補を見つけ出した死神には、次の死神大王へと昇格させる」という強いインセンティブがあったからです。映画冒頭のテロップと、最後のリュークの説明にありましたね。
死神大王は、人間の感情をコントロールし、巧みな人口調整を行ったキラの手腕を高く評価しており、キラ亡き後の世界の荒廃ぶりを目にして、新たな「キラ」探しの必要性を感じていました。リュークだけでなく、他の死神も競わせ、新生「キラ」を探し出すことで、人間界と死神の共存繁栄を狙っていたのです。
実際、一旦日本政府に収まった6冊のノートのうち、4冊は移送中に焼失しましたが、すぐに別のノートがどこからか降ってきているようですから、三島(新生竜崎)はこれからが大変になるわけです・・・。
7.原作マンガとの設定相違点(※ネタバレ有注意)
原作漫画とは、すでに2006年の実写版映画2部作の時点から設定やストーリーの展開が違っていますが、今作では実写版映画の流れを受け、さらに原作漫画から設定が広がっているのが特徴です。(でもみんな死んだけど・・・)
7-1.弥海砂が10年後に生きている
原作マンガでは、弥海砂は夜神月の死亡後1年後に亡くなっていましたが、映画実写版の世界では、女優として活動を続けていました。死者の目を2回契約し、さらにもう1回契約したならば、いずれにしても余命はほとんどなかったと考えられますね。
7-2.魅上について
原作マンガでは、魅上は夜神月が死亡した時、警察に逮捕され、10日後に発狂して死亡していたはずです。しかし、映画実写版では、2006年の2部作で出てきていないので、同名で別の役割が当てることができたのでしょうね。夜神月の狂信的な信者で、検事であるという設定は、マンガ版と共通しています。
7-3.夜神月の子供について
原作マンガでは夜神月に子供は勿論いませんでしたし、付き合ったのも高田清美・弥海砂と全員日本人でした。アメリカにどうやって種を残したのか、そのあたりの設定は不明ですが、これから公開されるんでしょうか・・・?!
ストーリーに味付けをするためだけに子供がいることにして、セリフもなしに殺さなくても良かったんじゃないかとは思います・・・
8.ノベライズ版との設定相違点(※ネタバレ有注意)
今作は映画のノベライズ版が出版されています。ライトノベル風で、割りとあっさり描かれた読みやすい文体です。基本的な展開、台詞回しは映画に忠実ですが、映画でやや乏しいと思われる状況説明を補完するシーンや一部映画と違う展開もあるので、非常に興味深く読めました。主な相違点をピックアップしておきます。
8-1.いっぱい出てくる死神たち
映画版で出てきたリューク、アーマ、ベポの他に、アレクセイに憑いたシドウ、そして御厨賢一についたイーヴという死神が出てきます。シドウはマンガ版後半で出てきたちょっとどんくさい性格そのものでした。ノベライズでは、紫苑にチョコレートをねだるかわいい一面もあります。せっかくなので、もう1体の死神(アメリカでデスノートを拾ったアーヴィングのデスノートの死神)にもちゃんと名前をつけてあげてほしかったです。
8-2.弥海砂と竜崎の対面シーン
ノベライズでは、紫苑が操った一般人が竜崎の仮面を剥いだところを弥海砂が見て、ノートに書き込む流れでしたが、映画では竜崎は自分で仮面を外していました。命をかけて「すでに別のノートに自分の名前が書かれていたか」確認する竜崎の決意や意志を強調するための演出だったのだと思います。
8-3.映画で省略された説明の補完
たとえば、以下の点が映画中では時間の都合上説明が省略されていましたが、ノベライズではバッチリ説明されていました。
・紫苑がアレクセイをデスノートで殺害する際の詳細なシーン
・アーヴィングのデスノート使用と紫苑に殺害されるまでの経緯
・甲羅山へ攻撃出動前の須賀原と日本政府のやり取り
・竜崎が三島と入れ替わる前の「超法規的措置」を取るに至った経緯
是非、読んで確認してみてください。
9.感想とまとめ
10年後の後日譚を描いた本作「DEATH NOTE デスノートLight up the NEW world」。
良かった点は、個々の俳優の頑張り。竜崎の、粗野でバイク好きのキャラクターが原作のメロに似ているところが非常に興味深かったです。紫苑の菅田将暉も、「カメレオン俳優」と言われるように、配役にぴったりあわせた演技が良かったですし、記憶を取り戻し、夜神月への思いを断ち切れない哀愁たっぷりの戸田恵梨香の演技も成長を感じられて良かった。
反面、従来の「謎解き」を期待していたファンにとっては、少し不満が残る展開だったのではないでしょうか。端的にいうと、この映画は「謎解き」ではなく、「アクションもの」と割り切ったほうがいいのかも(汗)
ストーリーや伏線はやや粗く、スピード感で押し切る場面が多かったような。設定もあいまいな点が残りました。竜崎はなぜデスノートを所持していたのか、誰もそれを問題にしないのか・・・あいまいな「約束の地」も少し不明確でした。Huluの前日譚やノベライズとのストーリーの効果的な補完もあまりうまく行っていない印象はあります。
それでも、「デスノート」の世界がより広がったのは良かったと思います。またアナザーストーリーに期待したいし、今回は今回で、僕個人としては味わい尽くせたかなと思います。
それではまた。
かるび
10.映画を楽しむための小説やガイドなど(随時追加)
10-1.ノベライズ版
今作「DEATH NOTE LNW」を忠実にノベライズ化した作品。謎解きをじっくり味わいたい人や、背景をより詳細に理解したい人にお勧め。映画の世界観を忠実に表現しているライトノベル仕立てです。
10-2.マンガ原作「デスノート」
やっぱり原点は漫画版原作。スリリングな謎解きに圧倒的に詰まった情報量。僕も今回Kindleで買い直しましたが、全巻で3000万部を売り上げただけある、不滅の名作だと改めて実感。映画公開に合わせ、Kindleカラー版1巻がAmazonにて期間限定で無料で読めるようになっていますので、この機会に是非!
10-3.Amazonの「デスノート」特設ページ
現在、Amazonで「デスノート」特設ページができています。こちらも過去作品を押さえる場合は便利。特に、2006年の実写映画「DEATH NOTE」「DEATH NOTE the Last name」が、今回の作品と直接関係があるので、まだ見たことが無い方は、是非藤原竜也と松山ケンイチの若い時の演技を楽しんでみて下さい!(満島ひかりとか戸田恵梨香も若いし!)





















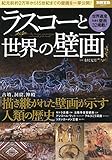






























































 日常生活を描く一方で、この映画は、すずと周作の恋愛映画でもあります。すずは、見ず知らずの家に就職面接をするかのように北條家へ嫁入りします。好きかどうかも分からない中、徐々に周作に惹かれていくすず。
日常生活を描く一方で、この映画は、すずと周作の恋愛映画でもあります。すずは、見ず知らずの家に就職面接をするかのように北條家へ嫁入りします。好きかどうかも分からない中、徐々に周作に惹かれていくすず。