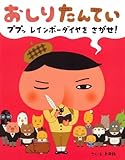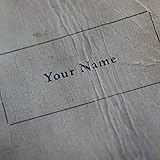かるび(@karub_imalive)です。
「君の名は。」で盛り上がる中、9月17日から封切りとなった映画「聲の形」。週刊少年マガジンでの、原作マンガの週刊連載時から、その優れたストーリー性と赤裸々な感情描写で話題でしたね。
![f:id:hisatsugu79:20160917003754p:plain f:id:hisatsugu79:20160917003754p:plain]()
僕も、リアルタイムで連載を読み、その後大今良時さんの過去作「マルドゥック・スクランブル」も後追いで読んだくらい一時期ハマったことがあったので、今回上映が決まったときから楽しみにしていました。
今日は、初日見てきた感想を中心に少し書いてみたいと思います。
※本エントリでは、映画のあらすじや感想、伏線などを書いていますが、ネタバレを含みます。ネタバレ部分を読みたくない方のために、ネタバレ有りの部分は明示しています。
1.「聲の形」映画基本情報
【ジャンル】アニメ・恋愛/青春映画
【公開日】2016年9月17日(土)
【監督】山田 尚子
【主題歌】aiko「恋をしたのは」
【サントラ】牛尾憲輔「a shape of light」
2.当日の映画館の様子・混雑状況など
前回「君の名は。」と同様、ユナイテッドシネマ豊洲の朝一9時10分の回に行ってきました。さすがに早朝だったので、座席の埋まり具合は7割くらい。熱心なファンが多く、グッズを片手に座席についている若い人が多かったです。「君の名は。」の時に若者の周りに座るのはなんとなく懲りたので、オッサンは端の方の席におりました・・・。
ある程度のヒットを見越して多めに上映回数が設定されているので、おそらく座れないほど混雑することはないと思いますが、土日連休の午後などは、席が取りづらい時があるかもしれません。
3.主要キャストと声優
予告PVで名前付きで紹介された主要キャストは、8名とかなり多めです。中でも、主人公はこの二人。
石田将也(いしだ しょうや/CV:入野自由)![f:id:hisatsugu79:20160917012146j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012146j:plain]()
クラスのガキ大将から、硝子との一件からいじめられるようになった小学生時代の心のキズをかかえ、自分を閉ざしたまま孤独な毎日を生きている。
西宮 硝子(にしみや しょうこ/CV:早見沙織)![f:id:hisatsugu79:20160917012206j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012206j:plain]()
先天性の聴覚障害により周りとのコミュニケーションに苦労し続けたため、自己評価が低い。いつもあやまってばかりで、自己主張より愛想笑いで争いを避けようとする。
つづいて、他のメインキャラ達。
西宮 結絃(にしみや ゆずる/CV:悠木碧)![f:id:hisatsugu79:20160917012317j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012317j:plain]()
翔子の妹。母親との関係は良いとはいえず、たびたび家出を繰り返す。自身のことを「オレ」と言い、翔子のことをいつも気遣っている。
植野 直花(うえの なおか/CV:金子有希)![f:id:hisatsugu79:20160917012221j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012221j:plain]()
小学校の頃からスクールカーストの上位にいた素直で活発なクラスの人気者だった。心の強さを備えた自信家だが、思ったことをすぐに口に出す不器用な性格で、好きな将也の心をつかめない。
永束 友宏(ながつか ともひろ/CV:小野賢章)![f:id:hisatsugu79:20160917012229j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012229j:plain]()
見栄っ張りな性格から、過去にたびたび友人を無くしてきたが、人懐っこくて熱いタイプ。本編では将也の心を最初に解きほぐすキーマンとなる。
佐原 みよこ(さはら みよこ/CV:石川由依)![f:id:hisatsugu79:20160917012322j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012322j:plain]()
小学校時代、皆が見捨てた硝子と唯一仲良く接した優しさを持つが、心の弱さが泣きどころ。高校生になり、自信をつけつつあるが、「成長」への強いこだわりを内に秘めている。
川井 みき(かわい みき/CV:潘めぐみ)![f:id:hisatsugu79:20160917012253j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012253j:plain]()
天然タイプの優等生タイプのお嬢様。自分のルックスに多少自信があり、時に良い子ぶって鼻につく言動も、実は「地」であり表裏はない。
真柴 智(ましば さとし/CV:豊永利行)![f:id:hisatsugu79:20160917012243j:plain f:id:hisatsugu79:20160917012243j:plain]()
高校での将也のクラスメイト。イケメン男子だが、子供への異常な執着心がある。「軽さ」の下に心の葛藤を隠している。
4.結末までのあらすじ(※ネタバレ注意)
多数のメインキャラクターが存在しますが、ストーリーは、石田将也の視点で進行します。主に、将也が小学校6年生の時と、高校3年生の春~秋にかけての2つの時期を描いていきます。
ガキ大将だった小学校6年生の石田将也は、いつも悪ガキ仲間とつるんで、面白いことを探す毎日でした。ある日、先天的に聴覚障害を抱える転校生の少女、西宮硝子が転校してきます。硝子は、耳が聴こえないため、筆談用ノートを使ってクラスでコミュニケーションを図るが、コミュニケーションはうまくいきません。
硝子への対応で、クラスメイトが翻弄され、疲弊していく状況を見て、将也も不器用ながら何度かコミュニケーションを試みますが、上手く通じません。
そのうち、硝子の存在を疎ましく感じるようになり、将也は、率先して硝子に対して辛くあたるようになってしまいます。 やがて、将也を中心にエスカレートした嫌がらせは、クラス全体を巻き込んだいじめへと発展していきます。
硝子の筆談ノートを学校の池に投げ込んだり、高額な補聴器を破損させ、硝子の耳にケガを負わせてしまうなど、目に見えて物理的な被害を出すに至り、先生が介入する事態に発展します。
先生が介入して問題解決へと当たった際に、将也はいじめの主犯格として断罪されます。しかし、クラスメイトは、先生の追及に対して将也一人のせいにして逃げてしまいます。これをきっかけに、将也はクラスで孤立し、一転していじめられる対象となってしまいました。
学校側からの連絡を受けた将也の母親は、硝子の母親へ謝罪し、補聴器代(170万円)を弁償します。謝罪から戻ってきた将也の母の耳からは血を流した痕跡がありました。
ある日、下校時にいつものようにいじめられ、学校の池に突き落とされる将也。起き上がる時、偶然硝子の大切にしていた筆談ノートが池に落ちていたことに気づき、(直接的な表現はないが)ノートを持ち帰ります。
また、別の機会に、将也は硝子と放課後に偶然1対1で鉢合わせになるシーンがありましたが、そこでも結局分かり合えず、二人は取っ組み合いのケンカをしてしまいます。
結局、硝子はクラスになじめず、別の学校に転校してしまうことになりましたが、一連の事件を通じて、将也は他人不信に陥り、同時に罪の意識を背負うことになりました。
それから5年後。高校3年生となった将也は、それ以来人間不信と自己嫌悪からずっと孤立し続けていましたが、硝子に一言、小学生時代に伝えられなかった謝罪をしてから自殺しようと決意します。
そして、硝子の通うろう学校に出掛け、再会します。この日のコミュニケーションに備え覚えた手話で、硝子と会話し、持っていた小学生の時の筆談ノートを返すとともに、とっさに「友だちになってくれ」と口走ってしまうのでした。
それより、二人は、毎週火曜日の午後、ろう学校近く水門橋の「鯉の餌やり」の時間に定期的に会うことに。
やがて、家出の際に家に泊めてやるなどして、姉思いの硝子の妹、結絃(ゆずる)とも仲良くなります。以降、結絃は硝子と将也の潤滑剤的な存在になっていきます。
また、学校では、高3の春にして、不良に絡まれていた所を助けてやった縁から、クラスの後ろの席の永束とも仲良くなり、徐々に将也の学校生活にも変化が出てきます。
将也は、硝子と仲良くしたため、クラスで孤立し不登校となってしまっていた小学校のクラスメイト、佐原みよこを硝子に引き合わせます。また、偶然街で鉢合わせした植野直花とも再会することになりました。
硝子は、やがて石田のことを好きになり、ある日、思い切って髪型をポニーテールにして、贈り物を渡すとともに、水門橋の前で肉声で思いを伝えますが、聴覚障害のため、上手く発声ができません。「好き」を「月」と勘違いされてしまい、将也には通じませんでした。
将也、硝子の仲間はさらに増えます。クラスメイトの川井みき、真柴智を加えて、仲間たちで遊園地に行くことに。遊園地では将也はジェットコースターで隣の席に座った佐原と会話し、また植野は観覧車で硝子と一緒に乗り、かつての過去のわだかまりを乗り越えつつあるかに見えました。
しかし、夏休み前に、同じメンバーでいつもの水門橋で会った際、川井と植野の言い争いをきっかけに、将也と仲間たちの関係は再びこじれ、仲間同士の関係は一旦壊れかけます。
夏休みとなり、仲間で集まるきっかけを失った将也は、硝子を元気づけようと焦り、連日硝子を外に連れ出します。その過程で、硝子の母と和解する機会も持てた将也は、硝子の家族と花火大会に一緒に出かけました。
硝子は花火大会の最中、なぜか「受験勉強があるから」と先に帰宅してしまいます。結絃から、カメラを自宅に忘れたから取りに行ってくれ、と頼まれ、将也は硝子の後を追って硝子の家に戻ります。
すると、硝子はベランダからまさに飛び降り自殺をするところでした。仰天した将也は、「硝子ぉ~」と大声を上げながら、必死で助けますが、硝子を引っ張り上げた拍子に、将也自身がベランダの下に転落してしまうのでした。
落ちた将也は、しばらくの間昏睡状態となります。将也が昏睡状態の間、関係者の間で様々な葛藤がありますが、ある日吹っ切れた硝子は、もう一度、将也の不在の間、仲間との関係改善にコミュニケーションを尽くすようになりました。
ある夜、硝子はリアルな夢を見ます。その夢は将也の死を暗示させるもので、真夜中に目が冷めてしまった硝子は、直感的にいつもの水門橋のところへ。
同じころ、将也は病院で昏睡状態から目覚めます。将也も、点滴を外し、導かれるように病院着のまま病院を抜け出し、水門橋へ。
二人は、真夜中に水門橋で会い、将也は、そこでこれまで口に出来なかった硝子への謝罪の気持ちを伝え、改めて、「生きることを手伝って欲しい」と硝子に伝えます。ここで、ようやく将也は硝子に対する悔恨、罪悪感と決別することができました。また、硝子も将也の言葉を受け入れ、前向きに生きることを決意します。
そして、夏休みが終わり、文化祭。復帰した将也は、硝子と将也の学校の文化祭に行きますが、そこで仲間たちから再び受け入れられ、ようやく真の意味で自分を取り戻す喜びを感じます。
ここで、映画は終幕となりました。
5.見終わっての感想(※ネタバレ注意)
映画「聲の形」は、主人公の将也の視点でストーリーが進んでいきます。主人公の将也が小学生の際に負った「罪悪感」「自己嫌悪」といった一種のカルマ的な心のキズと少しずつ向き合っていく中で、それに触発された仲間たちもそれぞれの自分の心の課題と対峙するようになります。
物語を通して丹念に描き出されるのは、徹底したキャラクター同士の生々しいコミュニケーションと、その難しさです。時に、負の感情をむき出しにし、醜く顔をそむけたくなるような言葉遣いや仕草で、お互いのわだかまりやエゴ、本音を直接相手にぶつけ合うのは、原作同様でした。
不器用でもいいから、ストレートなコミュニケーションを重ねて、お互いに認め合い、自分自身に赦しを出すことでしか、本当の意味で自分自身の心を癒やすことはできないのでしょうね。重たい心のキズに向き合い、自死を選ぶ直前まで追い詰められながら克服した将也、硝子の強さが印象的でした。
6.映画のみどころ・伏線など(※ネタバレ注意)
みどころ①:原作とのストーリーの違い
一番大きな違いは、原作で丹念に描かれた「文化祭」での映画撮影企画が全省略されているところと、将也が昏睡状態に陥っている際に描かれたサブキャラクター達の過去と向き合うサイドストーリー、原作終盤の学校卒業後の後日談の箇所がそれぞれカットされたところです。
次に、原作では殴り合いのシーンや言い合いのシーンは全体的にやりすぎな位生々しさが際立ち、人間の醜い表情もきっちり描き出されていましたが、若干その表現は全体的に抑えめとなっていました。原作ではたびたびヒール役として登場する小学校の担任、竹内先生の持つ「大人のいやらしさ」全開のシーンも全カットでしたね。
また、原作では主要キャラ8名を丁寧に描き分けていましたが、映画では時間の制約上、佐原、川井、真柴あたりは描ききれていない感じでした。
これらは、全7巻の内容を2時間少々に詰め込む中で、致し方ないところではありました。しかし、全体としてのストーリーの流れや、作品のテーマ、世界観はきっちり保持されていたかと思います。不満を覚えるほどの違和感はありませんでした。
みどころ②:なぜ硝子は唐突に自殺しようとしたのか
原作の時から謎だったことですが、このたび、最終回答が、「聲の形公式ファンブック」で原作者、大今良時氏から語られました。
硝子は自分のせいで壊したものを、ずっとカウントしています。自分のせいで親が離婚した。じぶんのせいで妹がいじめられた。自分のせいでクラスの雰囲気が悪くなった。自分のせいで佐原さんも学校に来なくなった。ぼんやりと「死にたい」と考えながら、そのカウントを積み重ねていたんです。[・・・]そうして将也と再会するわけですが、やっぱり彼と友達の関係を自分が壊してしまい、カウントと死への想いが甦り、橋の上で「やっぱり死のう」と決断してしまう・・・
つまり、ずっと自分の心の中では「死」を意識しており、直前に起こった事件により「自分がいると周りが不幸になる」と再認識してしまって、死を選ぼうとしたということですね。唐突な判断ではなく、以前から考え続けていた結果の行動でした。
みどころ③:「いじめ」や「聴覚障害」ではなく、「コミュニケーションそのもの」を描いたストーリー
これも、公式ファンブックやインタビューにて原作者が語っていることですが、「いじめ」や「聴覚障害」はあくまで設定であり、主題を強調するためのモチーフに過ぎないのです。実際、見終わって「やっぱりいじめはいけないな」「聴覚障害って大変なんだな」という感想にはならなかったのではないでしょうか?
それよりも、自分の犯した(と思っている)罪や罪悪感、伝えられなかった気持ち、コミュニケーションの難しさや、それらと傷つきながらも必死で対峙する主人公たちの心の動きに感動させられるはずです。
「君の名は。」が男女の体の入れ替わりというわかりやすい古典的な設定を使いつつも、決してそれに甘えずに、男女のすれ違いや思いを届けることの難しさをメインテーマに据えていたのと同じですね。良い映画は、安易な設定に頼り切ったりはしないということですね。
みどころ④:表裏一体、合わせ鏡のようなふたり
主人公の将也と硝子は、象徴的に表裏一体の存在として描かれていましたね。二人の共通点を挙げてみると、かなりあることに設定の妙を感じます。
・名前に「しょう」がつく。
・互いに、母子家庭の出身である。
・共に自己評価が低く、加害者意識が強いため、常に自己嫌悪に陥る。映画全編を通して二人はなんども「ごめんなさい」と痛々しいほど謝るシーンが多い。
・物語序盤で将也が自殺を試みれば、終盤で硝子が飛び降りようとする。
・物語序盤で将也が硝子をいじめれば、その後将也がいじめられる側に回る。
このあたりは、原作者が意図的に敷いた設定・伏線だと思いますが、調べればさらにまだまだあるのだろうと思います。
みどころ⑤:京アニの安定した作画のクオリティ
「けいおん!」「たまこまーけっと」の監督を務め、若いながら着実にステップアップしてきた山田監督の下、その作画は主要キャラからモブキャラまで、高レベルのクオリティだったと思います。
また、背景の作り込みも見事でした。何度も描かれた「鯉のいる水場の風景」やクライマックスの花火のシーン、場面転換時に時折挟まれる道端の草花などが印象的でした。
みどころ⑥:主題歌「aiko/恋をしたのは」もストーリーとよくマッチしていた
どこで流れるんだろう?と思ったら、最後の最後でしたね。余韻が残る中、心に残る印象的な曲でした。
aiko-36th SINGLE 『恋をしたのは』9.21 OUT
7.岐阜県民は必見?聖地巡礼企画も!
![f:id:hisatsugu79:20160917005432p:plain f:id:hisatsugu79:20160917005432p:plain]()
今回、「聲の形」のアニメの舞台となった水門市のモデルは、岐阜県大垣市。その大垣市は、聖地巡礼ツアーをやる気満々です。
すでに始まっていますが、9月2日~10月2日にかけて、専用アプリ内で用意された大垣市内のチェックポイント全てにチェックインが完了すると、抽選でオリジナルグッズがもらえるらしいです。詳しくはこちら。
スタンプラリー専用アプリダウンロードページ | 聖地巡礼マップ
また、事前にすでに主要な聖地を回ってきた地元ブロガーさんのブログエントリもありますので、紹介しておきますね。映画の舞台そのもので、すごく行きたくなりました。
8.まとめ
原作に比べるとストーリーは単純化され、わかりやすくデフォルメされていますが、感情表現は映像・音声で強化された分、かなりのインパクトがありました。最初から心打たれるシーンが沢山出てきて、泣き所だらけです。
原作を見た人、見てない人でそれぞれ少しずつ感想は違ってきそうですが、ハイレベルな作品であることは間違いありません。原作が良いと、素直に作り込めば自然に良い作品になりますね。西宮硝子役の早見沙織の演技も、素晴らしかったです。
明日以降、2周目を早々に行ってきたいと思います。聖地巡礼もしてみたいな~。
それではまた。
かるび
おまけ:2周目を楽しむためのマンガ・公式ガイドなど
Kindleは、9月17日現在、期間限定で1巻のみ購読無料となっています。原作は2015年の「このマンガがすごい2015・男編」で第1位となったとおり、クオリティは言うまでもなく高いです。後半部分、映画では省略された「映画作り」や文化祭後の後日談も味わい深いですよ。
まとめ買い用のリンクです。ご活用ください。全7巻なので、早ければ半日あれば読み終わると思います。
川崎 美羽,吉田 玲子 講談社 2016-09-16
小説も発売されました。上下巻での上巻が出たばかりですが、映画やマンガとは違った媒体で作品を味わうことで、今作のテーマ「コミュニケーションの難しさ、伝わらなさ」をリアルに味わうことができるかもしれませんね。
大今良時氏みずから、原作のポイントやコンセプト、伏線や設定の詳細についてを語り下ろした、ファン必携の書です。事実上の答え合わせのようなものですね。映画では省略された描写も含め、2周目を楽しむなら、欠かせない資料だと思います。連載前の「読み切り」バージョン(2013)、新人賞応募バージョン(2008)も収録されています。
こちらは、原作ファンのブロガーさんが、連載時から毎週感想や分析をブログに書いていた文章をご自身でまとめられたKindle本です。分析や読みのレベルが非常に深く、ファンサイドから本作を分析したリソースとしては、随一の出来です。公式ファンブックと合わせて読めば、映画がさらに楽しめます。Kindle Unlimited指定となっています。
大今良時のデビュー作。冲方丁の同名の原作SFアクションを、複雑な世界観を壊さず忠実に描ききった佳作です。えげつない表現は少年誌のレベルを越えているような気がしますが、聲の形でハマった人は、読んで損はないと思います。心をえぐり取るような激しい感情表現は、このデビュー作から遺憾なく描きこまれています。