
かるび(@karub_imalive)です。
6月21日から、日韓国交正常化50周年記念と銘打たれて、日韓両国を巡回して公開されている仏像展「ほほえみの御仏ー二つの半跏思惟像ー」展に行ってきました。結構印象深かったので、ちょっと書いてみたいと思います。
- 0.興味を持ったきっかけ
- 1.混雑状況と所要時間目安
- 2.「ほほえみの御仏展」のコンセプト
- 3.展示されている日韓の半跏思惟像
- 4.半跏思惟像のルーツと日本伝来の経緯って?
- 5.まとめ
- おまけ1:今回の展示会の予習/復習で役に立ったもの
- おまけ2:同時開催の「特別展 古代ギリシャー時空を超えた旅ー」もおすすめ!
0.興味を持ったきっかけ
個人的な話になりますが、僕の亡くなった祖父は、生前、零細出版社を経営していました。今はもう残念ながら倒産してしまったのですが、昭和高度成長時代、まだカラー写真印刷が珍しかった頃から、カラー写真を取り入れた図鑑や美術・風景などの学術系写真集を得意としていました。
そんなわけで、僕が小さい頃は、自宅や実家の書棚には、大量の祖父の出版社で出した本がストックされて飾られていました。軽く1,000冊以上はあったかなと思います。
中でも祖父が大事にしていた本が、「中宮寺半跏思惟像」が表紙になっている大型本の写真集で、いつも本棚の目立つところにおいてあったのです。
幼い時によく目にしていた日常風景っていうのは、本当に記憶に残っているものですよね。その写真集を見るたびに、「なんで笑いながらこの仏像寝てるんだろう」と不思議に思っていたものです。今回。そんな中宮寺の半跏思惟像が実際に上野に来るっていうので、これは見ておかないとな、ということで行ってきた次第です。
1.混雑状況と所要時間目安
さて、東京国立博物館・国宝・仏像・日本美術・・・と言えば、ちょっと美術展に通い慣れている人なら、なんとなく「混雑」というキーワードが頭に浮かんでくるかと思います(笑)
実際、過去の「阿修羅展」「皇室の名宝展」「長谷川等伯展」などはアホみたいに混雑しましたし、今回もどうなるのでしょう。
・・・と思って出かけたのですが、大江戸線を降りて、上野公園を横切り、公園奥の噴水前あたりに来た所で、すでに博物館のゲート前に遠巻きに列をなしているのを遠巻きに発見!!うわー、若冲展の時みたいになっちゃうの?!このアメなのに!!

一瞬、引き返して別の日に出直そうかと考えたのですが、先日の若冲展が、結局会期の後半になればなるほど混雑がひどくなっていったのを思い出し、意を決して雨に打たれながら渋滞の最後尾に取り付くことにしました。

そんなわけで軽く憤りながら軽くツイートでグチをこぼします。
仏像を見るのに並ぶのって日本人くらいのものでしょ。韓国での先行した展示会空いてたのに。
— かるび@あいむあらいぶ (@karub_imalive) June 21, 2016
で、傘に隠れてよく見えなかったのですが、どうしてゲート前で渋滞しているのかというと、手荷物検査が実施されていたからだったようです。

まぁ仕方がないですね。日韓の国宝だし、特に何か爆発等取り返しの付かないことになったら、時期も時期ですから、政治問題に発展しかねない。おとなしく並ぶこと10分で、ゲートを通過。手荷物検査は結構厳しかったですよ。アイドルやタレントのコンサートでよくある、形だけのカバンチェックじゃなくて、金属探知機も導入した、空港並みの厳重なチェックです。

で、コレを抜けると、渋滞は解消。正面の「日本館」1Fの特別展示室へ直行します。平日の午前中だったから、修学旅行生が多かったのが印象的でした。


入り口です。写真撮影はここまで。特別展示室内は、当然写真撮影禁止です。
2.「ほほえみの御仏展」のコンセプト
冒頭でも書きましたが、今年は日韓国交正常化50周年。これを記念して、古代における日韓の文化交流の象徴である「仏教伝来」をテーマに、日韓両国での仏像「半跏思惟像」を比較展示した企画展です。
すでに、先行して5月24日~6月12日の会期で、韓国国立中央博物館にて「特別展:韓日国宝半跏思惟像の出会い」展として、韓国側の展示が完了しています。20日間の会期で46,000人の動員実績でした。
韓国国立中央博物館
展示は、本当にシンプルで、特別室に、2つの仏像が向かい合ってガラスケースに入って置かれているだけです。余計なものは何もありません。もう、仏像をしっかりと見ていってくださいね、ということですね。
昔、ドラクロワの絵が来た時も「えっ、これ1枚かよ(笑)」と思いながら長蛇の列をなしたものですが、今回もそれくらいの希少性はあると思います。是非、穴のあくまで見つめて行ってください(笑)イメージ図としては、こんな感じ。

3.展示されている日韓の半跏思惟像
3-1:韓国国宝第78号 半跏思惟像

制作地は不明。制作年は、朝鮮半島の三国時代(高句麗、百済、新羅)である6世紀後半頃に鋳造されたと見られています。韓国では、国宝を第◯◯号、と数字で管理しているのですね。
像高83.2cm、座高52.3cm、台座30.9cmと非常に小ぶりの仏像でした。日本の中宮寺の仏像の半分くらいの大きさです。なんと木彫りではなく金銅像。非常に高い鋳造技術を持っていたことがわかります。頭には宝冠が乗り、詳細なデザイン、洗練された天衣などの表現は、王室のお抱え彫師によるものだと言われています。
3-2:中宮寺 半跏思惟像

これに対して、日本側の半跏思惟像です。奈良の飛鳥地方、法隆寺のちょうど隣にある古刹「中宮寺」に安置されている弥勒菩薩像です。韓国の78号より50~100年後の制作で、7世紀後半くらいに制作されました。
像高126.1cm、座高87.9cm、台座高79.6cm。仏像としてはよくある大きさでしょうか。78号と見比べると、1.5~2倍位の大きさに見えます。
頭頂はおだんご頭で、2つに髪を結った古代のヘアスタイルです。木造で、漆塗りのため黒光りして、時代の経過をあまり感じさせません。よく見ると、体の一部に彩色がしてあったり、昔は装身具も身にまとっていた形跡があります。止利仏師の2代後くらいの彫師が複数のクスノキ木材をつなぎ合わせて制作しました。
飛鳥時代の近畿地方では、当時良い石が採石できず、その代わりに木材は豊富に産出していたことから、木材で作られたと言われています。
4.半跏思惟像のルーツと日本伝来の経緯って?
半跏思惟像(はんかしゆいぞう)とは、右脚を左膝の上に組んで座り、右手を頬に添えて物思いにふける仏像のことを言います。日常風景でも、テスト中とか電車の中で寝てる人とかたまにこんな格好してますよね・・・。
(引用元:ほほえみの御仏 二つの半跏思惟像 × 聖おにいさん)
本来は、出家前の釈迦が修行中に思い悩むところを表現した姿勢としてインドから伝わってきました。敦煌莫高窟や、雲崗石窟寺院などでは、釈迦そのものを表わす石像としてデザインされました。
しかし、仏教朝鮮半島に伝わった段階で、当時信仰が盛んだった弥勒菩薩信仰と合体し、朝鮮では弥勒菩薩として半跏思惟像が制作されるようになります。
仏滅から56億7千万年後にこの世に救世主として顕現する弥勒菩薩が、人々の救済を願い、思い悩むポーズがちょうど半跏思惟像にぴったりだったので、イメージを重ねあわせられたのだと言われています。
ところで、6世紀後半は、朝鮮半島は百済・新羅・高句麗の3国が相争う戦乱の時代でした。日本書紀によると、劣勢だった百済の聖明王は、新羅に何とか対抗するために、日本へ仏教伝来・指導と引き換えに日本に軍事支援を要請しました。西暦577年、造仏工、造寺工が1名ずつ百済から来日しています。
日本史の教科書にも出てくる「止利仏師」(鞍作鳥)が、この時来日した百済の仏師から必死に学び、制作した、日本における第一世代の仏像が、法隆寺釈迦三尊像や、飛鳥寺の飛鳥大仏です。見てもらえればわかりますが、この2体は顔の表情が、「国宝78号」と似てるんですよね。
法隆寺釈迦三尊像
中宮寺 飛鳥大仏
また、7世紀には、今度は新羅が日本との軍事交流のため、広隆寺に仏像を送ってきています。(623年、日本書紀による)これが、通称、「宝冠弥勒」と呼ばれ、日本の国宝第1号に指定された広隆寺の半跏思惟像です。*1
広隆寺 宝冠弥勒
これが、同じく旧新羅統治エリアから発掘された韓国国宝第83号とソックリなんですよね。頭の宝冠の形や、下半身の天衣の表現など。見比べてみてください。
韓国国宝 第83号
このあたりからも、飛鳥時代当時の、仏教伝来における朝鮮半島と日本の強い結びつきを感じられますよね。こうやって丹念に歴史と合わせて見ていくと本当に勉強になるし、面白いです。古くからの友人としての日韓の友好を記念としたテーマとして、ぴったりだったかなと感じました。
5.まとめ
あれこれブログに書きましたが、日本美術は、特に「現地に行って」実物を見てくるのが一番だと思います。中宮寺や広隆寺はまぁ京都奈良に行けば今後も見る機会はありますが、韓国の78号のほうはこれを逃すと非常に実物を見るのは難しいです。
僕も、子供の頃からずっと写真集だけで見てきた、中宮寺のおだんご頭の半跏思惟像を初めてリアルで見て非常に感銘を受けました。幼い時の記憶通り、優しい微笑みをたたえた仏様で、ちょっと嬉しかったです。優しい顔をした中性な体躯をした仏像は本当に魅力的でした。会期も短いですから、是非時間を作って足を運んでもらえるといいと思います。
おまけ1:今回の展示会の予習/復習で役に立ったもの
今回ブログで紹介したネタは、実は展示会がスタートする直前、6月15日にNHK総合で放送された「日韓の国宝が海を超えた~半跏思惟像はるかな旅」での放送内容を大きく参考にしています。
今のところ、再放送予定は決まっていないようですが、オンデマンド等でチェックすると、さらに理解が進んで良いと思います。
また、この一部引用させてもらいましたが、「聖☆お兄さん」の特別コラボマンガは面白いので強くおすすめです(笑)東京国立博物館もなかなかやりますね。
おまけ2:同時開催の「特別展 古代ギリシャー時空を超えた旅ー」もおすすめ!
このあと、ほほえみの御仏展の左奥の「平成館」で6/21から開催されている古代ギリシャ展に行ってきたのですが、これがかなり良かったです。東洋の仏像とはかなり趣は違いますが、同じく古代ギリシャ時代の貴重な展示物が何と大量325点も展示されています!!ほんと、1日で回りきれないくらいの充実展示でした。
ほほえみの御仏展自体は、10分程度で見終わっちゃいますので、その後本館の常設展示を見るもよし、古代ギリシャ展に回るのもよし、どちらでも面白いと思います!
それではまた。
かるび
*1:※ただし、最近の研究だと材質などから日本で作られた可能性もあるとのことです。






































































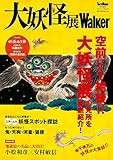




















































 (引用:
(引用:









 葛飾応為「夜桜美人図」
葛飾応為「夜桜美人図」

























