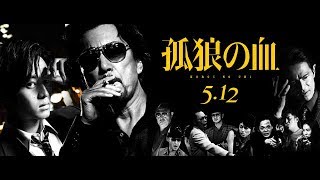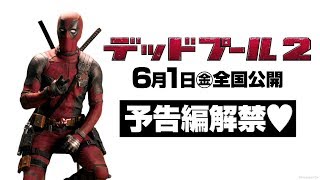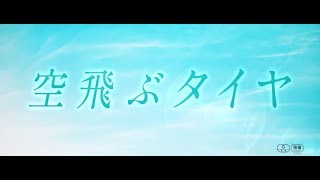かるび(@karub_imalive)です。
3月30日に公開されたフランス発SFアドベンチャー映画「ヴァレリアン 千の惑星の救世主」を見てきました。春休みの映画激戦区シーズンに公開された影響もあり、公開初週から興収・動員数ベスト10圏外に沈んでしまい、僕の近くでは今週末(4月12日)上映終了になる映画館もちらほら・・・。
でも、これがかなり自分としては気に入ったSF作品だったんですよね。最初から最後まで、ワクワクしながら映画を見れたのは本当に久しぶりでした!早速ですが、興奮冷めやらぬ中、感想・考察等を織り交ぜた映画レビューを書いてみたいと思います。
※本エントリは、後半部分でストーリー核心部分にかかわるネタバレ記述が一部含まれますので、何卒ご了承ください。できれば、映画鑑賞後にご覧頂ければ幸いです。
- 1.映画「ヴァレリアン千の惑星の救世主」の予告動画・基本情報
- 2.主要登場人物・キャスト
- 3.途中までの簡単なあらすじ
- 4.映画内容の簡単なレビュー!(感想・評価含め)
- 5.映画で登場する主な宇宙人・クリーチャーたちをまとめて紹介!
- 6.映画「ヴァレリアン」に関する9つの疑問点~伏線・設定を徹底考察!(※強くネタバレが入ります)~
- 疑問点1:ヴァレリアンとローレリーヌの関係性とは?なぜ、ヴァレリアンはいきなり求婚しているのか?
- 疑問点2:ヴァレリアンとローレリーヌの本作における当初の任務とは?
- 疑問点3:「ヴァレリアン 千の惑星の救世主」での宇宙の歴史をまとめてみた
- 疑問点4:アルファ宇宙ステーションとはどんな存在なのか
- 疑問点5:パール人はなぜ滅んだのか?その後なぜアルファ宇宙ステーションのコア部分に住み着いたのか?
- 疑問点6:物語の核心に絡む「ミュール変換器」とは?
- 疑問点7:ローレリーヌをさらった「ブーラン・バソール」とはどんな種族なのか?
- 疑問点8:ラストシーン・結末の考察~フィフス・エレメントと似ていたエンディング~
- 疑問点9:続編はあるの?
- 7.映画パンフレットも買ってみた
- 8.まとめ
- 9.映画をより楽しむためのおすすめ関連映画・書籍など
1.映画「ヴァレリアン千の惑星の救世主」の予告動画・基本情報
【監督】リュック・ベッソン(「フィフス・エレメント」「ルーシー」)
【配給】キノフィルムズ
【時間】137分
【原作】ピエール・クリスタン/ジャン=クロード・メジエール「ヴァレリアン」シリーズより
本作を手がけたのはフランス出身の巨匠、リュック・ベッソン監督。最近は彼が設立したEuropa Corpのアクション・サスペンス系作品のプロデューサー業に徹していましたが、今回は久々に監督/脚本を自ら務める力の入った作品となりました。

引用:Wikipediaより
最近は色々「切れ味がなくなった」「つまらなくなった」とベテラン映画ファンから辛口コメントをもらいがちな監督の常連となってしまった感がありますが、自身がメガホンを取った作品は、「グランブルー」「レオン」「ニキータ」と、なんだかんだ名作揃いなのであります。
SFアクション・アドベンチャー系では、「フィフス・エレメント」や、スカーレット・ヨハンソンが主役の「ルーシー」などが有名ですね。
そんなリュック・ベッソン監督が、構想約20年、着手から7年かけて、フランス映画史上最大となる約2億ユーロ(≒約260億円)を投入して作り上げた作品が本作「ヴァレリアン 千の惑星の救世主」です。
実は、本作は原案として、フランスを代表するSF系バンドデシネ(マンガ)の古典「ヴァレリアン」シリーズを土台としており、リュック・ベッソン監督は幼少時から何度も何度も読み返した、非常に思い入れのある作品なのだそうです。
その物語が持つ広大な世界観や、監督の思い入れ、本作の製作背景を理解するのにぴったりの紹介動画「3分でわかるヴァレリアン」が、キノフィルムズからリリースされています。これは、映画を見る前でも、見た後でも、チェックしておくと、より深く作品理解ができるので、視聴おすすめです!
2.主要登場人物・キャスト
ヴァレリアン(デイン・デハーン)
引用:映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』小悪魔編(18秒)|
優秀だけどナルシストで自信家、そして軽くてチャラいプレイボーイ、という役柄を見事に演じきりました。実年齢は30代ですが、映画内では見事にローレリーヌと同じか、それより精神年齢が確実に低い感じの頼りなさをしっかり出せています。なお、2018年公開予定「チューリップ熱」でもカーラ・デルヴィーニュと共演しています。
ローレリーヌ(カーラ・デルヴィーニュ)
引用:映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』小悪魔編(18秒)|
ナタリー・ポートマンやミラ・ジョヴォビッチなど、これまでも数々の新人原石系女優を大作で抜擢・発掘してきたベッソン監督。今回新たにオーディションで選んだのは、元カリスマモデルのイギリス人若手女優、カーラ・デルヴィーニュ。前作「スーサイド・スクワッド」に続く大役をゲットし、さらに本作のサントラで、歌手デビューも果たすなど、いよいよブレイク間近でしょうか?
フィリット司令官(クライヴ・オーウェン)
引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna z
代表作「キング・アーサー」での主演が激シブだっただけに、今回、かなり情けない司令官役にはびっくり。どことなく、顔つきがルー大柴に似てきたような?(そう思うのは僕だけ?)
バブル(リアーナ)
引用:『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』バブル(リアーナ)ダンス映像|
シナリオ後半の一番大事な部分で、彼女が本筋とは関係の薄いダンスを披露するシーンは、正直「このシーン、いるの?」と思いましたが、ダンス自体はキレキレで、見応え充分。流石に一流歌手は舞台度胸はしっかりしています。
客引きジョリー(イーサン・ホーク)
引用:『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』バブル(リアーナ)ダンス映像|
誰だこのオッサンと訝しげに思い、あとからクレジットを見て愕然!イーサン・ホークのSFオススメ作品といえば、「ガタカ」(1997)ですが、あのかっこよかったイーサン・ホークはどこへ?????しかしリアーナ同様、この人の役柄も本筋には何ら関係がなかったですね(笑)
3.途中までの簡単なあらすじ
西暦2740年。1975年に地球人によって建設が始まった宇宙ステーションは、それから約200年後、地球を離れ、全宇宙から集まってきた何千もの種族が集まって暮らす、巨大なコロニー、「アルファ宇宙ステーション」となっていた。
宇宙に飛び出した人間は、宇宙人との連邦政府を樹立し、全宇宙で活動するようになっていたが、そんな連邦政府の若き捜査官、ヴァレリアンとローレリーヌは、この日も惑星キリアンでの特殊任務に当たっていた。二人は、すでにコンビを組むようになって2年。ヴァレリアンは女癖の悪い、軽い男性とみなされていたが、ローレリーヌの聡明さと強さ、頭脳明晰さに惚れ込んでいた。彼は、思い切って任務前にローレリーヌに求婚した。ローレリーヌは、特殊任務が終わったら返事をする、とサラッとかわしたが、内心悪い気はしなかった。
彼ら2人に与えられた任務とは、今や滅亡してしまった惑星ミュールでかつて生息していたが、今や宇宙でたった1頭となってしまった小動物「ミュール変換器」を、惑星キリアンに本拠地を置く海賊、アイゴン・サイラスから奪還することだった。
惑星キリアンでVR空間上に築かれた巨大商業都市、ビッグ・マーケットでアイゴン・サイラスを追い詰め、VRマシーンの不具合にもかかわらず「ミュール変換器」を奪還したヴァレリアン達は、久々にアルファ宇宙ステーションへと帰還することになった。
帰還した二人の次の任務は、最近宇宙ステーションで拡大中の「放射線汚染エリア」の調査任務だった。その過程で、フィリット司令官の護衛についた二人だったが、護衛中にトラブルが起きた。フィリットが何者か未知の種族にさらわれたのだ。ヴァレリアンは、すぐに追跡用のジェット「スカイジェット」に乗り込み、そのエイリアンを追いかけるが、追跡中にスカイジェットが操縦不能になり墜落してしまう。
ヴァレリアンの身を案じたローレリーヌは、上官の静止を振り切り、情報屋を使って単独でヴァレリアンの居場所を突き止めるのだった。
しかし、二人が合流したのもつかの間、今度はローレリーヌが攻撃的なエイリアン、ブーラン・バソール族に捕まってしまう。ヴァレリアンは、ローレリーヌの救出のため、姿を自由に変えられるエイリアン、グラムポッド族のバブルの力を借りて、ブーラン・バソールの王宮へと忍び込む。そして、なんとかローレリーヌと合流したのだが、彼らが合流した地点は、任務で調査対象エリアとなっていた「放射線汚染エリア」指定地域だった。同エリアは、実際には放射線には汚染されておらず、この地区に居住していたのは、なんと30年前に絶滅したはずの惑星ミュールに住んでいたパール人だった。
二人は、そこでパール人の哀しい秘密と、自らの上官・フィリットが犯した重大な罪を知り、ある重大な決断を迫られることになったのだったーーー。果たして、彼らの出した結論は?また、ヴァレリアンとローレリーヌの恋の行方はどうなるのか?
4.映画内容の簡単なレビュー!(感想・評価含め)
ハリウッドとは「何か」が違うフランス流の大作SFアクション映画
本作はリュック・ベッソン監督が仕上げた大作SF作品と聞いて、観る前は「まぁ、ハリウッド作品と同じような感じなのかな」と思って見ていたら、既存のハリウッド作品とはやっぱりテイストがちょっと違っているのが面白いですね。
まず、映画冒頭から最後まで、基本的には主人公ヴァレリアンとローレリーヌの二人の愛と冒険の物語になっていて、男女1対1の関係性が深く掘り下げられて描かれます。表面上は男女関係の恋愛ゲームを楽しんでいるような感じに見えて、深いところではお互いに深く信頼しあっている二人は、劇中で様々な危機が迫るたびに、お互いの名前を叫ぶのです。このあたりは、過去2年間のコンビを通じて、数々のピンチを乗り切ってきた二人の絆の強さでもありますが、そんな2人が、本作で起こる巨大な事件を通じて、今度は仕事上のパートナーから人生のパートナーへと変わっていく、その過程をじっくり、じっくりと描いていくのが印象的でした。
こうなると他の登場人物は、もうハッキリ脇役ですよね。名優、クライヴ・オーウェンもカッコ悪い悪役ですし、イーサン・ホークもリアーナも、ほぼ使い捨てであります(笑)豊富に用意されたクリーチャーやエイリアンたちの存在も、二人のストーリーを盛り上げるためだけにいるような感じで、どこまでも二人の世界を中心に演出が組まれているのですよね。ハリウッドでよくある、シリーズ化への伏線がたっぷり張られた群像劇とは一線を画したこの徹底ぶり、良かったです。

引用:映画『ヴァレリアン 千の惑星の救世主』最終予告(60秒)
そして、映画冒頭から密室で際どい水着姿の二人が絡んでいるところが映し出され、いきなりヴァレリアンが激しくローレリーヌに求婚を迫る展開に始まり、最後はやはり二人だけの密室で終わるラストシーン。このあたりもさすがフランス流の映画でした。フランスだと職務中にずーっと耳元で結婚しよう、と囁いてもセクハラにはならないのでしょうか(笑)
タイトルは「ヴァレリアン」だけど、事実上ローレリーヌが主役の本作
実はベースにしている原作ではもっとハッキリそうなのですが、本作では全体的にダメで情けない男性のキャラクターに比べて、女性キャラクターの強さ・明晰さが目立ちました。

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
特に、ローレリーヌは美しいだけでなく、頭もよくて芯の強いキャラクターとして描かれます。映画冒頭こそ、ヴァレリアンの副官として控えめで殊勝にしていますが、危機が高まってくる中盤以降、特にヴァレリアンが倒れてからはグイグイ前に出てきて、行動作戦面においてはヴァレリアンをリードするようになってきます。最後のキスも自分からですし・・・
映画ラストでパール族のために究極の選択を行うシーンでも、まだ地位や立場、建前にこだわり、最良の選択肢への逡巡を見せるヴァレリアンに対して、より本質的で臨機応変に正しい判断ができたローレリーヌ。美しいだけでなく、心も強く、愛情も深い無敵のキャラなのですよね。
パンフレットでも言及されていましたが、全体的に、本作では男性キャラが地位や名誉、立場、利益などに固執し、人間として正しくない行動を取ってしまう反面、女性キャラの聡明さ、バランスの良さが強調されて描かれました。
昔のように、単に美しく、エロく演出されるだけでなく、女性の「強さ」がどう作品内で表現されるかが、最近の映画作品の一つの見どころですよね。「スター・ウォーズ」や「モアナと伝説の海」「ズートピア」「美女と野獣」といった最近のディズニー大作映画もそうですが、時代はハッキリ女性的な感性・感覚を求めているのだなと感じた作品でもありました。
「フィフス・エレメント」の正常進化版?こだわり抜かれたビジュアル面の演出
かつてベッソン監督が「フィフス・エレメント」を撮った時、彼が頭に思い描いたビジュアル面の全てが満足に表現できたわけではなかったといいます。当時はまだCG/VFXを活用した特撮技術が未発達だったのですね。
あれから、20年。まるで過去消化不良だった鬱憤を晴らすかのように、ものすごい種類が用意されたエイリアンたちや、彼らのコロニーの多様性や、演出のアイデアは、見ているだけでもワクワクする豪華さがありました。1作品だけで何十種類も出てくるエイリアンの種類は、スター・ウォーズやスタートレックといった名作を遥かに凌いでいますし、惑星キリアンでのビッグ・マーケット内でのVR世界と実世界を股にかけた複雑なアクション演出は、見応えたっぷりでした。
どんな厳しいレビューを見ても、その驚愕の映像表現だけは、けなしている記事を一つも見たことがありません。ぜひ、映画館でやっているうちにガッツリ大画面でチェックしてみて下さい!
スポンサーリンク
5.映画で登場する主な宇宙人・クリーチャーたちをまとめて紹介!
本作で特に力を入れて作り込まれたのが、数々の宇宙人やクリーチャーたち。ベッソン監督は、企画段階でクリエイティブ系クラウドソーシングを活用し、世界中から3000以上集まったデザイン案から20ほど厳選して採用したとのこと。ここでは、映画で登場する主なクリーチャーを、特徴をピックアップしながら紹介しますね。
◯アイゴン・サイラス

引用:Valerian and the City of a Thousand Planets | "This Thing is Priceless" Clip | Own It Now
惑星キリアンを縄張りとして、古物や美術品を取り扱う宇宙海賊。攻撃的な性格のコダール・ハーン種族で、鼻に3つの鼻腔があることが特徴。(乾季、雨季、冬と3つの季節が存在するコダール・ハーン族の母星の気候に適応)パール人ツウリの依頼で、真珠とミュール変換器を集めたが、パール人達との交渉の席で、ヴァレリアンに両方とも奪われた。
◯シールト族

引用:Valerian and the City of a Thousand Planets | "Imagination" TV Commercial |
惑星キリアンのビッグマーケットで雇われ、警備を担当していたヒト型爬虫類。知能は低めだが、温厚な種族。人懐っこさゆえに気が散りやすい性格で、彼らの文化は「利益」「通貨」という概念を持たない。そのため、本来は警備員として長期雇用されることに本質的に向いていない。
◯メガプトール

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
惑星キリアンで、アイゴン・サイラスが飼っていた、6本脚と鋭い鉤爪を持つ獰猛な肉食獣。ビッグマーケットから逃げるヴァレリアン達を捕食すべく放たれたが、離陸するイントルーダーに噛み付いたまま、同機のワープ時に上空に放り出されて不運な最期を遂げた。
◯オムライト族

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
ステーション北部に巨大なコロニーを構築し、大きい頭と長い腕を持っている有機体と金属で構成された体を持つ痩せ型の宇宙人。主に情報技術・金融に強いとされている。
◯アジン・モウ族

引用:映画「ヴァレリアン オフィシャルサイト」より
どんな細胞も生成する特殊能力を持つ医師集団で、神経科学に精通しており、ステーション東部に巨大コロニーを構築している。アジン・モウ族は、ステーションに何百ものファームを運営し、その中できらきら光る、様々な遺伝物質が詰まった「核クラスター」という柔らかい玉をメンテナンスしている。
◯ドーガン・ダギーズ

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
いつも3体一組で行動する、金にうるさい民間の情報屋。5000の言語を話す情報通で、連邦政府高官に情報を高く売りつけることを生業の一つとする。本作では、ローレリーヌに接近し、ヴァレリアンの行方探しを手伝った。
◯グラムポッド族(バブル)

引用:Meet Bubble: Rihanna Talks Valerian - YouTube
自由に姿を変えられる特殊能力を持った宇宙人。青いゼリー状で半透明の体を持つ。本作で登場する「バブル」は、宇宙ステーション内でも身寄りのない寂しい「ブーラン・バソール」に囚われたローレリーヌの居場所へ潜入するため、ヴァレリアンを助けた。
◯ブロモサウルス

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
爬虫類と昆虫を足して2で割ったような巨大な水棲生物。硬い甲羅と短い脚を8本持つ。水面下にあるステーション南部の液体の中に生息しており、体長は64メートルと超巨大。普段はおとなしく、ガラナ海の深みに生息している。
◯コーテックスクラゲ(皮質クラゲ)

引用:Cara Delevingne - I Feel Everything (From "Valerian and the City of a Thousand Planets")
ガラナ海の深みで、ブロモサウルスの吐き出す純水を摂取することでしか生きられず、ブロモサウルスの頭部に寄生して生息する。このクラゲに頭から肩まですっぽり入ることで、観たい対象者のイメージを伝えると、対象者の記憶を垣間見ることができる。

引用:Cara Delevingne - I Feel Everything (From "Valerian and the City of a Thousand Planets")
ただし、長時間は無理で、目安として1分までとされており、1分をすぎると記憶を吸い取られてしまうリスクがある。(ローレリーヌは1分10秒耐えた)
スポンサーリンク
6.映画「ヴァレリアン」に関する9つの疑問点~伏線・設定を徹底考察!(※強くネタバレが入ります)~
ストーリーや設定について、本作をより深く・面白く鑑賞するために要点となりそうなポイントについて、考察や情報をまとめています。内容上、映画を1度見終わった人向けのコンテンツとなりますので、ここからはネタバレ要素が強めに入ります。予めご了承下さい。
疑問点1:ヴァレリアンとローレリーヌの関係性とは?なぜ、ヴァレリアンはいきなり求婚しているのか?
ヴァレリアンとローレリーヌは、宇宙政府の連邦捜査官として、コンビを組んで2年になっていました。幼い時に両親を亡くしたヴァレリアンは、17歳から捜査官になってから、その勤勉さと有能さを認められ、昇進を重ねていましたが、一方で母親の愛を知らない彼は、理想の女性を求めて、女性との交際を繰り返すプレイボーイでもありました。
しかし、2年前から副官としてコンビを組んでいるローレリーヌは、美しく、頭もよく、行動力もある、優しさと強さを兼ね備えた女性で、ヴァレリアンが巡り合った女性の中で、No.1の理想だったのですね。だから、彼は映画冒頭でローレリーヌに求婚していたのです。でも、映画中ずっと口説きっぱなしの展開は、いつものハリウッド的な映画の作りとは違い、いかにもフランス映画っぽい展開だなぁと思いますよね。
疑問点2:ヴァレリアンとローレリーヌの本作における当初の任務とは?

引用:Valerian and the City of a Thousand Planets | "Imagination" TV Commercial |
連邦捜査官であるヴァレリアンとローレリーヌの当初の任務とは、惑星キリアンで骨董品店を営む海賊・アイゴン・サイラスから、「ミュール変換器」を奪還することでした。「ミュール変換器」は、その希少性から人間連盟の保有生物となっていたのです。
疑問点3:「ヴァレリアン 千の惑星の救世主」での宇宙の歴史をまとめてみた

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
ヴァレリアンの世界は、西暦28世紀ですが、映画冒頭では、プロローグとしてそれまでの人類の歴史が簡単に紹介されました。以下、簡単にまとめてみました。
・1998年:アルファ宇宙ステーションで、多国籍のドッキングに成功。
・2019年:中国の巨大宇宙船、天宮3号がアルファに接続。国際的な緊張関係終焉の象徴となる。
・2027年:アルファでの居住人数が8000名を突破。
・2029年:各国からの1名以上の科学者が選出され、各国代表としてステーションへ滞在するようになる。
・2031年:ステーションに人工重力システムが導入される。
・2150年:ステーションは全長3kmに拡大、居住者数は10万人を突破。この年、人類は初めて宇宙人とのファースト・コンタクトを経験。コータン・ダフーク族との接触があった。その後、ステーションの重量過多による地球への落下を危惧した地球政府は、ステーションを地球の軌道外から外宇宙へと出航させた。
疑問点4:アルファ宇宙ステーションとはどんな存在なのか
元々は地球で作られ、少しずつ膨張を繰り返す中で、外宇宙へと移動した宇宙ステーションの名称です。28世紀には、宇宙で暮らすほぼ全ての知能を持つ生物が訪問し、交流するうちに住み着き、現在は宇宙最大のステーションへと膨張しました。今も毎年数%ずつ物理的なエリアが拡大しており、現在の直径は約20km弱で、3236もの種族、約3000万人が暮らし、5000を超える言語が使われています。それぞれのエリアには各宇宙人のコロニーが形成されており、水棲動物なども住み着いていました。ドーガン・ダギーズのような多言語を自由に操れる特殊能力を持つ種族には、格好の稼ぎ場ですよね。
疑問点5:パール人はなぜ滅んだのか?その後なぜアルファ宇宙ステーションのコア部分に住み着いたのか?
元々惑星ミュールに住んでいたパール人は、30年前、惑星軌道上で行われた戦争に巻き込まれ、その際、核融合爆弾を打ち込まれたことで、王族以下数十名を除き、全滅してしまったのです。

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
その後、彼らは上空から墜落して半壊した宇宙船に咄嗟に乗り込み、これを使って惑星ミュールを脱出します。惑星ミュールが爆発し、帰るところのなくなった彼らは、宇宙船の中で必死に人類文明や学問を学び、環境へと適応したのでした。

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
その後、彼らは別の商船に乗り込み、アルファ宇宙ステーションへとたどり着き、人知れず情報を集め、社会を観察し、ステーションの深奥部に彼ら自身のコロニーを建設したのです。彼ら独自の技術を使い、外部には「放射線汚染区域」とみせかけることで、人を寄せ付けずに上手く偽装してきたのですね。

引用:Valerian and the City of a Thousand Planets | Final Trailer |
ちなみに、パール人は、死ぬ時に全エネルギーを宇宙へと四散させるため、その魂が誰か別の人間へと入り込むことがあります。惑星ミュール滅亡時、宇宙船へ乗り遅れたプリンセス・リホは、爆発する惑星と最後を共にしましたが、彼女が爆散させたエネルギーを、たまたま任務外で寝ていたヴァレリアンがキャッチしてしまい、以来、ヴァレリアンの心の中にはリホが住み着いていたというわけです。
疑問点6:物語の核心に絡む「ミュール変換器」とは?

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
ミュール変換器は、元ミュール星に生息していたクリーチャーで、あらゆるものを複製できる特殊能力を持ちます。ウランを主食としており、元気な時は体表が七色に光ります。ミュール星が爆破されたことをきっかけに、全宇宙で1匹だけになってしまった絶滅危惧種として、連邦政府で保護されていましたが、海賊アイゴン・サイラスに奪われ、所在がわからなくなっていました。
物語中では、ローレリーヌは試しに自ら持っていたダイヤモンドをミュール変換器に複製させていましたね。
疑問点7:ローレリーヌをさらった「ブーラン・バソール」とはどんな種族なのか?

引用:VALERIAN Official Trailer # 2 (2017) Cara Delevingne, Dane DeHaan, Rihanna
宇宙ステーションとブーラン・バソール族の間は現在緊張関係にあり、現在の皇帝ブーラン3世は、他種族が彼らの縄張りに入ることを禁止していました。政治的実権は、皇后「麗しのノバ」が握っており、皇帝ブーラン3世は、豪勢な食事を楽しむことのみでした。映画内でも、次々に運ばれてくる(ゲテモノ?)料理を一口味見しては捨ててましたね。そのメインディッシュとされたのが、彼らの縄張りでさらわれたローレリーヌだったというわけです。
ちなみに、ヴァレリアンは、幼少期、母・サラがかつてステーションの拡大方針に反対するブーラン・バソール族との和平交渉にあたった際、爆殺されてしまい、母を失いました。次いで、父も彼の元を離れていくなど、同種族との関わりには、個人的にも複雑な思いがあったと思われます。
疑問点8:ラストシーン・結末の考察~フィフス・エレメントと似ていたエンディング~
アルファ宇宙ステーションの古いコアの深遠部を占拠して自らの居住区を作り、そこで密かに宇宙船の建設を進めていたパール族。彼らの滅亡の原因は、30年前、パール人が居住していることを知りながら、戦局を有利に進めるためにミュール星へと核融合爆弾での爆撃を行った上官、フィリットにありました。さらに、その不都合な事実を画すため、関係者を粛清して、関連するデータベースを削除、アクセス不能にするなど、フィリットの卑劣な行動も明るみになります。
パール族は、ミュール変換器を取り戻し、彼らの「真珠」(莫大なエネルギーをその中に蓄積している)をミュール変換器を使って複製することで、建造した脱出用の宇宙船の動力エネルギーにしようと計画していました。
フィリットの逮捕には積極的だったヴァレリアンでしたが、「愛」と「信頼」に基づいてミュール変換器を、その元々の持ち主であったパール人へと独断で返却しようとするローレリーヌに対して、彼は最初頑なに「任務」に忠実であろうとして、返還を渋ります。より本質的で、直接的な解決策は明らかにローレリーヌの判断なのですが、こういう時に組織べったりで、守るべきもの(地位や名誉)がある男性は弱いですね。土壇場で、守りに入ってしまう・・・。
しかし、ローレリーヌの強い押しに説得されて、彼女の判断を信頼し受け入れたヴァレリアンも、ミュール変換器をパール人へ返すことに同意します。
こうしてミュール変換器を使って「真珠」を複製してエネルギー源を確保したパール人は、間一髪、フィリットのロボット部隊を使った捨て身の妨害を振り切り、ヴァレリアとローレリーヌと一緒にアルファ宇宙ステーションを脱出していきました。
そして場面は変わってラストシーン。やはり外宇宙のどこかで、古代の宇宙船(密閉空間)で救援を待つ間、再度プロポーズしたヴァレリアンに対して、ローレリーヌはやっと彼の気持ちを受け入れ、二人は結ばれてハッピーエンドとなるのでした・・・。このシーン、どこかで既視感が・・・と思ったら、ほぼ「フィフス・エレメント」のラストと同じなのですよね。色々あったけど、最後は愛する二人が幸せになって終わり、二人の愛は全てんい勝る・・・といったテイストのラストシーンは気持ちの良い終わり方でした。
疑問点9:続編はあるの?

引用:Wikipediaより
日本でも苦戦中の本作ですが、本国フランスはともかく、アメリカを始め世界各国でも興収が伸びず苦戦。これによってベッソン監督の製作会社Europa Corpは2017年末時点で1億3500万ドルの赤字を計上し、役員の責任問題にも発展する事態となりました。当然続編はもう無理かな、と思っていたのですが・・・。
なんと、まだまだベッソン監督はやる気満々でした(笑)
各種報道によると、第2弾の脚本は書き終え、第3弾のシナリオ作りに着手中なのだとか。さすがに、この状況だけにベッソン監督も、「第2作以降は予算規模を縮小して、やれる範囲で・・・」と現実感ある構想になっているようですが、ちゃんと続編プロジェクトは存在していました!
別のソースでは、「NetflixがEuropa Corpへ買収の打診をしている・・・」との報道もあるので、ひょっとしたら、第2弾以降は、Netflixオリジナルドラマで見れちゃうかもしれませんね?!どんな形でもいいので、続編が見たい!楽しみです!
7.映画パンフレットも買ってみた

本作「ヴァレリアン」のパンフレットは、マーベルのアメコミ系作品ほど超充実しているわけではないですが、質量ともにかなり力が入っているのは確かです。
特に良いなと思ったのは、コラムとビジュアル面のバランスの良さ。映画評論家3名によるコラムに加え、監督/キャスト陣インタビュー、詳細なプロダクションノート、原作紹介など、しっかりしています。
特に村山章氏のコラムは、「惑星ミュールの冒頭シーンがダサい」「(リュック・ベッソンは)映画監督として一貫性と精細を欠き・・・」と書きたい放題。軽くベッソンをディスりながら、作品をしっかり持ち上げるという絶妙なバランス感の辛口コラムが最高!キノフィルムズの開き直った率直な編集姿勢、素晴らしかったです(笑)

そして、登場人物紹介だけでなく、クリーチャーや宇宙人の詳細解説も充実していたのは嬉しい限り。

さらに、本作最大の「ウリ」でもあるビジュアル面での斬新な演出・美術がよく振り返ることができるようにしっかり映画内の各シーンも収録されています。



毎回必ずパンフを購入する僕としては、今回は率直に「買い」だと思いました。 調べてみたら、Amazon等でも買えるようになっているみたいなので、リンクを置いておきますね。
8.まとめ
様々なエイリアンやクリーチャー、美術、セットを見ているだけでも楽しめる本作。ハリウッド流とは色々な意味で一線を画すストーリー、演出スタイル、フレッシュな主演陣の活躍も好感が持てました。日本でも興行で大苦戦しているようですが、個人的には非常に大好きな思い出深い作品となりました。ブルーレイが出たら絶対買います!
それではまた。
かるび
9.映画をより楽しむためのおすすめ関連映画・書籍など
完成度高し!ノベライズ版「ヴァレリアン」
「スター・ウォーズ」「スター・トレック」シリーズなどのハイクオリティなノベライズ作品で定評のあるクリスティ・ゴールデンによる書き下ろし。映画に忠実なストーリーテリングでありながら、映画では収録しきれなかったキャラクターの各場面での個別の心理描写や、ヴァレリアン、ローレリーヌについての逸話が描かれており、非常にクオリティの高いノベライズ作品に仕上がっています。訳も秀逸で、ストレス無く一気読みしちゃいました。おすすめできるノベライズです!
原作バンド・デシネ版「ヴァレリアン」
原作全23巻の中から、特に映画の原案として断片的に使われた「千の惑星の帝国」(1971)と「影の大使」(1975)の2章をまるっと収録し、作品解説と、リュック・ベッソン監督と原作者達の特別対談を収録した、映画の原点とも言える作品集。僕はこの作品でフランスの漫画「バンド・デシネ」を本格的に読んだのですが、非常にアメコミの影響を強く受けた作風に感じました。絵柄はまさに古き良きアメコミですが、ストーリーや舞台設定は、40年経った今でも全く色あせない意外性・楽しさがあります。
映画「フィフス・エレメント」
同じくリュック・ベッソン監督が手がけた壮大な宇宙を舞台としたSF冒険アクションもの映画で、本作「ヴァレリアン 千の惑星の救世主」のルーツとも言える作品。実際にフィフス・エレメントで大切な役割を果たす宇宙人「モンドシャワン人」他複数の人種が、ヴァレリアンにカメオ出演するなど、キャラクター造形、美術、セット、映像演出において類似点が多数あります。
また、「フィフス・エレメント」は、コミック「ヴァレリアン」第15巻"The Circles of Power"を原案とし、ここから着想を得ていると言われています。ヴァレリアンを見てリュック・ベッソン監督のSFに入っていくなら、合わせて見ておくといいですね!
リュック・ベッソン監督作品は、まとめてU-NEXTで!

本作を見て、リュック・ベッソン監督の作品をもっと見てみたいなと思った人は、豊富な作品群が用意されていて、その大半が「見放題」となっているU-NEXTで配信版を見て、ビデオ・オンデマンドで時間とお金を節約してみてはいかがでしょうか。
リュック・ベッソン監督がプロデュース・監督として関わった過去作は全部27作品配信中で、うち、代表作「レオン」「ニキータ」など、実に22作品を「見放題」でチェックすることが出来るのです。(2018年4月10日現在)
★最初の31日間は無料!
加入後、最初の31日間は会員料金が無料です。見放題以外の有料作品も、初月付与される600ポイントを使えば、2本まで無料で見れます。さらに、毎月自動的に1200ポイント付与されるため、月額料金も、実質上業界最安クラスの800円なのですよね。国内最大120,000点の品揃えは映画ファンにはたまりません!
★100誌以上の雑誌も読み放題!
DVDだけでなく、雑誌まで読み放題サービスがついてくるんですね。僕も、映画以外にもサブカル、マンガ、エンタメ系の情報はU-NEXTで無料購読できる雑誌から仕入れています!毎月付与される1200ポイントで、電子書籍を購入することもできますよ!