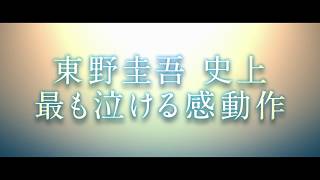【2018年3月2日更新】
かるび(@karub_imalive)です。
9月24日に公開された東野圭吾の大ベストセラーの映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」を見てきました。1980年と、2012年の間で、時空を超えて、「ナミヤ雑貨店」でやりとりされた「手紙」を巡って描かれたファンタジー色の強い群像劇。「泣ける」「感動!」と事前の評判は上々でしたが、果たしてどうだったでしょうか?早速ですが、映画を見てきた感想やレビュー、映画の内容・ポイントなど、詳しい解説を書いてみたいと思います。
※本エントリは、後半でストーリー核心部分にかかわるネタバレ記述が含まれますので、何卒ご了承ください。できれば、映画鑑賞後にご覧頂ければ幸いです。
- 1.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」の予告動画・基本情報
- 2.映画「ナミヤ雑貨店の奇跡」主要登場人物・キャスト
- 3.途中までの簡単なあらすじ
- 4.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」の感想・評価
- 5.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」に関する10の疑問点~伏線・設定を徹底考察!~
- 6.パンフレットにも泣ける演出が!
- 7.もう1本見るなら!東野圭吾の【泣ける】映画3選
- 8.まとめ
- 9.映画をより楽しむためのおすすめ関連映画・書籍など
1.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」の予告動画・基本情報
【監督】廣木隆一(「PとJK」「余命一ヶ月の花嫁」「ストロボ・エッジ」他)
【配給】KADOKAWA・松竹
【時間】129分
【原作】東野圭吾「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
東野圭吾作品の中でも、「最も泣ける」と大評判だった原作。時代を超えた連作群像劇の中で、時代を超えて複雑に絡み合ったストーリーが、最後に劇的な収束を迎える展開は、東野圭吾作品の真骨頂とも言えました。僕も読みながら泣きました・・・。
ただし、これを実写映画化するとなると、話は違ってきます。映画化は非常に難易度が高く、主要作品の大半が早々に映画化されてきた東野圭吾作品の中では、最後まで手がつけられずに残っていた印象です。
今回これに果敢に挑戦したのは、ベテラン職人映画監督・廣木隆一でした。(現場が好きな監督なので、頼まれれば基本的に嫌だとは言わないのかもしれませんが・・・^_^;)
ここ数年は、主に若者向けの青春学園恋愛スイーツ系を主戦場としていましたが、元々ピンク映画出身らしく、その守備範囲は広く人情物からアクション、サスペンスまで何でもこなす生粋の職人気質な監督です。意外にも、「ファンタジー」要素のある作品は、今回の「ナミヤ雑貨店の奇蹟」が初めてなんだとか。
廣木隆一監督といえば、なんといってもあの、ねっとりと動く「引き」のクレーンカメラやドローン撮影を多用する独特の映像演出ですね。
クレーンカメラが大活躍!
引用:映画公式パンフレットより
例えば、学園ものだと主人公が1Fから3Fまで階段を登っていくシーンを、吹き抜けからクレーンカメラでねっとりと追いかけたり(ストーカー目線?!)、カメラが上空すぎて主人公たちが一瞬どこにいるのかわからなくなる「ウォーリーをさがせ」状態だったり、カメラワークが面白いなぁと思うところが結構あります。
「ストロボ・エッジ」とか「オオカミ少女と黒王子」「PとJK」あたりでは、「そこ、今二人がいいところなのにカメラ引きすぎじゃね??!!」とイラッとする場面もありました(笑)
でも、今回の「ナミヤ雑貨店の奇蹟」では、その独特の引きの映像が、逆に幻想的・神秘的なファンタジー色を程よく醸し出すプラスの効果があるように感じました。是非、廣木監督作品を初見の方は、この独自の「カメラワーク」を味わってみてくださいね。
2.映画「ナミヤ雑貨店の奇跡」主要登場人物・キャスト
本作は、大量の豪華キャストと登用した群像劇となっています。名前の通った俳優だけでも15人以上起用するなど、映画ならではのゴージャスな俳優陣を揃えてきました。ここでは、本当に主役級の7人のみ、簡単に触れておきますね。
主要登場人物
浪矢雄治(西田敏行)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
代表作「釣りバカ日誌」シリーズや、「探偵ナイトスクープ」や「人生の楽園」など中高年向けの番組MCなどから、昭和の人情・ノスタルジーを体現するアイコンになりつつある西田敏行。浪矢雄治はまさにはまり役でした。手術、糖尿病治療等で、一時期よりかなり痩せたかな?という印象。その分、ガンで亡くなる前のシーンは妙に病的でリアルな表情が撮れていました。
敦也(山田涼介)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
ジャニーズが映画配信に消極的なので、今まで過去作を見たことがなかったのですが、「暗殺教室」(計2本)「グラスホッパー」など、映画作品にもコンスタントに出続けているだけあって、演技力はそれなりでした。2017年10月には同じく主演の大規模公開映画「鋼の錬金術師」が控えており、今年は映画で勝負する年になりそうです。
翔太(村上虹郎)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編- YouTube
今年に入って「武曲」「二度目の夏、二度と会えない君」など精力的に絶賛売り出し中の二世タレントですね。(母親:UA)今、20歳ですが、舌っ足らずで童顔なので、あと5年くらいは学生役いけるかも?廣木隆一作品では、「夏美のホタル」以来、2度目の起用となりました。
幸平(寛一郎)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編- YouTube
2017年、俳優として映画デビューとなり、実写映画「心が叫びたがってるんだ」では、演技力はともかく、外見的にはアニメキャラのイメージそっくりの野球部員が再現されていました。村上虹郎同様、ベテラン俳優佐藤浩市を父に持つ二世タレントです。(三國連太郎から数えて三代目?!)
松岡克郎(林遣都)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
林遣都っていつの間にこんなに増量してたんでしょう?自分の中では、未だに「風が強く吹いている」(2009)でデビューした時の、痩身の駅伝ランナーというイメージが離れないのですが、今作ではすっかり「売れないミュージシャン」オーラ全開のなりきりぶりが良かったです。
セリ(門脇麦)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
村上虹郎同様、廣木組では2度めの起用。「オオカミ少女と黒王子」ではひたすら主演・二階堂ふみの引き立て役でしたが、今回はガッツリ見せ場のある良い役でした。歌いっぷりは、松任谷由実のような独特の声色が妙に印象に残りましたし、本人即興での振り付けで踊ったという海岸でのダンスも風景に上手くハマっていました。演技だけでなく歌もダンスも起用にこなせる実力派女優として存在感を示した作品でした。
田村晴美(尾野真千子)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編- YouTube
19歳のホステス役から51歳の女社長まで、唯一1980年と2012年の両方を演じましたが、やっぱりどちらもちょっと無理があったかも(笑)特に、19歳には見えなかった・・・。設定には難がありましたが、演技力に関してはいつもの申し分ない安定感でした。
皆月暁子(成海璃子)
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
前作「古都」以来、久々の映画出演。子役時代から、背伸びして実年齢にプラスした役も演じていたこともあり、もう30代くらいのイメージだったのですが、未だ24歳なんですよね。本作では、服装が昭和初期の「モガ」っていう感じでした・・・
3.途中までの簡単なあらすじ
児童養護施設「丸光園」出身の敦也、翔太、幸平の3人は、ある裕福な女性起業家の自宅に盗みに入ったが、逃走用のため空き地に止めてあった車が故障したため、彼らは走って逃げ、一晩だけ身を隠せる空き家「ナミヤ雑貨店」に忍び込んだ。
一息ついた時、店のシャッターの郵便口から突如差し込まれた1通の手紙に気がついた3人は、手紙をけてみると、その差出人は「魚屋ミュージシャン」と書かれており、日付は1980年となっていた。店の中に置いてあった古い雑誌記事から、かつての空き家の店主浪矢雄治が、生前に悩み相談で評判になっていたことを知った。
敦之は、誰かのいたずらだろうと取り合わなかったが、店を出て街を彷徨うと、不思議な事にまたナミヤ雑貨店前まで戻ってきてしまった。彼らは、思いつきで「魚屋ミュージシャン」に手紙の返信を書くと、すぐさま第2の返信がシャッターに差し込まれた。
やがて、彼らはナミヤ雑貨店シャッターの郵便口と、裏口の牛乳箱を通じて、彼らのいる2012年と1980年が不思議な力でつながっていることを知る。
そして、何人かの手紙に返信を重ねる中で、彼ら3人は、全ての相談者、登場人物たちが、何らかの形で3人の出身施設「丸光園」と関係があり、不思議な力で時空を超えて縁が結ばれていることを知っていくー。そんな中、彼らはネットで「ナミヤ雑貨店1夜限りの復活」と書かれた奇妙なページを見つけるのだったー。
スポンサーリンク
4.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」の感想・評価
ノスタルジーとファンタジーが程よくミックスされたまずまずの感動系作品
まず、最初に見て感じたのは、1960年代、70年代ではなく、1980年という世界ですら、すでに大衆文化の中では昭和的な懐かしさの文脈で語られるような時代になってきたのだなということ。雑貨屋という舞台セット、牛乳箱、商店街の街灯、町の魚屋、路面電車、主演に「昭和」を強く想起させる西田敏行が起用されたことなどは、明らかに「ALWAYS三丁目の夕日」路線の昭和懐古趣味を入れてきているなという印象。
自分が年を取ったのだなと言う事実を突きつけられるようで、見ていて複雑な心境になりました(笑)
実は、原作はもっと露骨なのです。小説内でサザンオールスターズの「みんなのうた」(1988)、ビートルズファンのバー、映画「エイリアン」(1979)、モスクワオリンピック(1980)、昭和天皇の崩御(1988)など、ノスタルジックな設定やキーワードが意図的に多めに入れられており、最初に一読した際は、いわば東野圭吾版「ALWAYS三丁目の夕日」なのかと思いました。

豊後高田の美しい遠浅な海岸も非常に印象的
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
映画では、CG/VFX向けの予算・ノウハウがそこまでなかったのか、小説ほど露骨に昭和美化路線には入らず、代わりに、ファンタジー色、ご当地映画色(ロケ地:豊後高田市)が強めに入っていました。どうしても「手紙」を全文読ませる形で進行していくため、若干オジサンの説教臭くなりがちな原作小説のアクを消しつつ、若いお客さんにも訴求した、絶妙のバランスだったように思います。
東野圭吾作品特有の絶妙なまとまり感
本作では、なぜ「ナミヤ雑貨店」彼ら3人が時空を超えた手紙のやり取りができるのか?という疑問には一切答えません。
そこは若干不満が残るところではありますが、それさえ与件・前提として一旦受け入れてしまうと、ものすごくストーリーの構成がかっちりしていて、エンディングに向けてパズルのピースがはまるように伏線が回収されていきます。選択肢がほとんどなく、ほぼ一直線に進んでいくロールプレイングゲームを解いているような感じですね。良い意味でも悪い意味でも、わかりやすく話の筋が整理されていました。
多少前半のエピソードが間延びしても、前半で広がった様々なストーリーが、時系列を越えてエンディングへと収束していく構成は、東野圭吾作品ならではの安心感でしょうか?鑑賞者に考えさせる余地は余り与えないものの、ストーリーを追っていく楽しさがある映画でした。
どうしようもない若者の確かな成長を描かれた点が印象的
僕が本作の一番の見どころと考える点は、若者3人(敦也、翔太、幸平)の一夜での特別な体験を経て大きく変わり、成長した姿を描いた部分です。
両親からの本当の愛情を知らず、将来の自己像も見えず、自尊心が低いまま、若さのエネルギーだけを持て余して大人になった地方の若者たち。彼らの、行き場のない不満・不安・諦念/閉塞感は、中盤までの敦也の演技に実によく反映されています。
しかし、彼らは突如として超常的な異空間に入り込み、そこで夜通し他人の人生相談と向き合うことで、同時に自分自身に真剣に向き合うことになります。
3人は、相談者たちが、まさに自分たちのアドバイスに従い、真摯に行動し続けてポジティブな結果を出したことで、「行動すれば可能性は開けていく」という事実を知るとともに、自分たちが初めて他人のために役立ったという実感を得て、クライマックスで大きく意識が変わり、劇的に成長を果たしました。
ここでも、やっぱりファンタジー的な異空間を雑貨店の周囲に作り出したことが、彼らのBEFORE/AFTERを劇的に演出する強い効果を生み出していたと思います。

一夜明け、大きく成長した若者たち
引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編- YouTube
若い時って、例えば合宿や旅行先などの非日常空間において何かきっかけを掴むと一夜で大きく自分が変わったことを実感できる経験って結構ありますよね?映画内で朝になって、達観したような表情の3人を見た時、「いや、まだまだ自分もここから変われるはず!」と、主人公のやんちゃな3人から勇気をもらえたような気がした、そんな映画でした。
スポンサーリンク
5.映画「ナミヤ雑貨店の奇蹟」に関する10の疑問点~伏線・設定を徹底考察!~
本作は、劇中で15名以上の俳優と、4つのエピソードを一気に紹介したため、かなりの設定・伏線に関する説明が省略されています。ここでは、より映画を立体的に深く理解するため、劇中で分かりづらかった10個のポイントに絞って解説してみたいと思います。ここからは、ネタバレ要素が強めに入りますので、閲覧については何卒ご注意下さい。
疑問点1:主人公達が入所していた「丸光園」とは?
主人公たちが入所していた「丸光園」とは、静岡県時越市に前館長、皆月暁子が建てた児童養護施設です。児童養護施設とは、保護者がいなかったり、虐待されていたりして保護する必要がある1歳~18歳までの子供を預かり育てる施設のことです。
元々戦前から地主として裕福だった皆月家で、両親が亡くなってから資産を相続した暁子は、戦争などで孤児となってしまった子どもたちを救うため、私費を投じて「丸光園」を創立したのでした。
疑問点2:手紙を通した時系列はどうなっていたの?
本作では、約120分の本編内で、実に10回以上目まぐるしく時間軸が変わります。でも、それほど難しく捉える必要はありません。基本的には1980年(浪矢雄治や相談者達)と2012年(敦也達の時間)を行ったり来たりするだけです。そこで、映画パンフレットを元に、1980年と2012年の出来事をわかりやすく整理してみました。
▼映画内での出来事を整理してみる
映画を理解する際に大雑把に抑えておくべきこととしては、細かい因果関係は別にして、以下の2つだけです。
・浪矢雄治が膵臓がんで入院して亡くなるまでの3ヶ月間、2012年12月20日にナミヤ雑貨店に迷い込んだ敦也たちが、浪矢雄治の代わりに相談者の対応にあたった。
・浪矢雄治が亡くなる1980年12月20日、未来からの感謝の手紙と、敦也からの白紙が浪矢雄治の元に届いた。浪矢雄治は亡くなる前、最後の返信を敦也に託した。
疑問点3:なぜ浪矢雄治は悩み相談をやっていたの?
1960年代、まだ浪矢雄治が元気で、ナミヤ雑貨店も繁盛していた時、彼は子供がいたずら的に始めた悩み相談を、半分とんちで返すような、子供相手の「余興」としてスタートさせました。「生協の白石さん」的な掲示板上での楽しいやり取りですね。
しかし、その後徐々に子供だけでなく、大人まで含めて「本気の」人生相談が入るようになったため、個別に「牛乳箱に」翌日までに返信する形で対応しているうちに、評判が評判を呼び、いつのまにか週刊誌で取り上げられるような本気の悩み相談へと変わっていったんですね。
いつしか、悩み相談は、浪矢雄治にとって生きがいになっていきました。1970年代以降、商店街の衰退とともにナミヤ雑貨店も客足が細り、売上が立たなくなるのに店を閉めようとしなかったのは、いつの間にか悩み相談が浪矢雄治のライフワークとなっていたからですね。
疑問点4:成海璃子扮する皆月暁子とは?どんな人だったの?

引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
皆月暁子は、児童養護施設「丸光園」の創設者で、戦前の1930年代、浪矢雄治と付き合っていました。小説によると、機械工(労働者階級)だった浪矢雄治と、地主の家系(上層階級)だった皆月暁子は、階級差を越えて一緒になるために駆け落ちを計画しますが、周囲に感づかれて未遂に終わります。
二人はそこで大人たちに引き離されることになり、浪矢雄治はそのあと別の女性と結婚しましたが、暁子は生涯浪矢雄治以外の男性とは結婚しないと心に決めて、丸光園の経営に心血を注いだのでした。暁子は、元々体が弱く、心臓の病気で1969年(or1970年)に亡くなっています。
浪矢雄治が亡くなる直前、暁子が雄治だけに見える形で出てきたのは、映画ならではのファンタジー演出を強化すると共に、暁子の存在こそが時空を越えて丸光園の関係者を結びつけたことを印象づける効果がありましたね。
疑問点5:敦也、翔太、幸平の3人は、どんな過去を持っていたの?また、なぜ強盗に入ったのか?

引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
敦也の母は22歳の時、敦也を産みます。水商売のお店でバーテンをしていた年下の男が父親でしたが、間もなく父親は行方がわからなくなり、母子家庭となりました。しかし、同棲中の母の恋人から度重なる虐待を受けた上、母の育児放棄により小2の冬、飢えて食べ物を万引きした際に貧血で倒れます。それから3ヶ月後、丸光園に預けられたのでした。
彼ら3人は同い年で、中高とも一緒だったので、学生時代には置き引き、万引き、自販機荒らし、空き巣など、暴力を使わない窃盗行為をゲーム感覚で楽しんできた過去がありました。
満18歳になり、翔太、幸平、敦也は丸光園を出ましたが、折からの不況で、翔太は家電ショップをクビになり、幸平は働いていた自動車工場が倒産し、敦也は部品工場で度重なるパワハラに嫌気が指して辞めていました。一方で、自分たちの育った丸光園が地元の成金によってラブホに変えられてしまうという噂は捨て置けず、3人共金がなかったこともあり、「懲らしめてお金を取る」ため強盗に入ったのでした。
疑問点6:浪矢雄治の遺言の中身とは?
浪矢雄治の遺言は、ざっくりいうと「自身の死亡した命日(1980年12月20日)の三十三回忌になる日に、『雄治のアドバイスの結果、相談者たちの人生がどう変わったか、手紙を雑貨店のシャッター郵便ポストに投函して報告して欲しい』という広告・告知を打つこと」でした。この遺言は、親族の手により実行されます。
疑問点7:インターネットでのナミヤ雑貨店のHPは誰が作ったのか?
浪矢雄治の遺言は、2012年になってから、インターネットのホームページ上での臨時告知として実行されました。映画では省略されましたが、原作小説によると、浪矢雄治の息子、貴之ではなく、貴之の孫、浪矢駿吾によって実行されました。つまり、浪矢雄治の曾孫(ひまご)ですね。
33回忌の当日、すでに貴之はこの世になく、貴之は亡くなる前、みずからの(子供ではなく)孫にネット上での告知を依頼したのですね。
疑問点8:皆月館長が亡くなってから丸光園に何が起きたのか?
丸光園は、前館長である皆月良和が2003年に亡くなってから、その長男が経営を引き継ぎましたが、長男が経営する本業の不動産業で膨大な赤字を出し、経営の実権が苅谷という副館長に移ると共に、経営破綻の危機にありました。苅谷は、経営の実権を握ると、職員の水増し登録などを行い、行政に補助金を不正申請していたことが、晴美の独自調査によって判明します。
晴美は苅谷に出資や経営の交代を申し出ましたが、苅谷は自らが手を染めている補助金の不正受給を知られたくないため、晴美の申し出に乗り気ではなかったのですね。
疑問点9:ラストシーン・エピローグの解釈は?登場人物たちのその後は?

引用:映画『ナミヤ雑貨店の奇蹟』予告編(手紙編) - YouTube
エンドロールと共に、今回の映画での主人公たちの「その後」が簡単に描かれたのは、映画オリジナルの描写でした。簡単にまとめてみると・・・
・敦也・・・看護師の見習い実習中
・幸平・・・料理人として修行中
・翔太・・・航空機の整備工場で勤務中
・セリ・・・ミュージシャンとしてライブ活動中
・映子・・・セリのマネージャーになった
・克郎・・・路上ライブでパフォーマンス(生前)
・晴美・・・丸光園の経営と手紙相談を引き継ぐ
敦也、幸平、翔太はともかく、晴美が浪矢雄治の手紙相談まで復活させて引き継いでいたのは、目頭が熱くなるサプライズ展開でした。
疑問点10:原作で省略されたエピソードや、原作との違いは?
映画では、尺の都合上、省略されたエピソードや、原作からの一部改変があります。かなり原作に忠実な出来でしたが、主な違いを、一応下記にまとめておきますね。
・北沢静子(晴美の親友)から、モスクワオリンピックを目指す道か、余命の短い重病の彼氏の看病に専念するか相談をするエピソードがカットされている。(対応したのは浪矢雄治ではなく敦也達3人)
・両親の夜逃げ計画に当惑した和久浩介が浪矢雄治に相談するエピソードがカットされている。
・インターネットでナミヤ雑貨店復活のHP対応を行う浪矢駿吾のエピソードがカットされている。
・時間が、オリジナルでは2012年9月13日となっている。(映画公開時期に合わせてずらしたか?)
・小説版では、皆月暁子は地の文章に出てくるだけで、浪矢雄治の前に(霊として?)登場することはない。
・小説版では、3人は幻の路面電車に遭遇しない。
・小説版では、ナミヤ雑貨店の中と外では時間の流れ方が違う。中の方が早い。しかし、裏口を開けっ放しにすると、時間の流れ方は同じになる。
6.パンフレットにも泣ける演出が!
そして、今回の映画パンフレットには、ちょっとした嬉しいサプライズ演出がありました!最初のページと最後のページに、手描き印字の浪矢雄治から敦也に当てたのラスト・レターと、それに対して敦也が書いたものの、出さなかった浪矢雄治へのお礼の手紙が封入されていました。(最初見た時は、全く気づかなかった^_^;)
▼表紙(浪矢雄治→敦也へのラストレター)
▼裏表紙(敦也→浪矢雄治への返信)
実生活などで挫けそうになった時、このパンフレットで浪矢雄治が死ぬ前に敦也に最後に宛てた渾身のメッセージ
あなたの未来はまだ白紙です。白紙だからどんな未来も描けます。全てがアナタ次第なのです。何もかもが自由で可能性は無限に広がっています。
という一文を読むと、なんだか勇気が出てくるような気がしますね。映画の内容を忘れてしまっても、この浪矢雄治のメッセージだけは心に刻み込んでおきたいと思いました。ちなみに、パンフレットは映画館で発売中ですが、Amazonでも出ているようなので一応リンクを置いておきますね。
7.もう1本見るなら!東野圭吾の【泣ける】映画3選
最近では、もう刊行するたびに必ずと言っていいほど映画化・ドラマ化される東野圭吾ですが、手がけるジャンルは刑事ドラマ、人情物、サスペンスなどかなり多岐に渡ります。ここでは、「ナミヤ雑貨店の奇蹟」を機に、次に見るべき東野圭吾の泣ける作品を3つ厳選して紹介しますね。
7-1.広末涼子の一人二役が好演!「秘密」
僕自身、東野圭吾作品の中でダントツに好きな作品です。1999年に広末涼子、小林薫主演で映画化されました。当時、世代No.1の人気若手女優として頭角を表した広末涼子が、小林薫を相手に妻と娘の一人二役を演じています。ラストシーンのどんでん返しでは涙腺決壊間違い無しです!
7-2.加賀恭一郎シリーズの傑作「麒麟の翼」
TBSでドラマ化もされた阿部寛扮する「加賀恭一郎」シリーズの中で、映画化されたエピソードです。 2012年当時、社会問題となっていた派遣切りや労災隠しなど、時事ネタも採り入れつつ、父と子の親子愛をテーマに描いた作品。主役に新垣結衣、中井貴一、松坂桃李を据えて、当時まだブレイク前だった18歳頃の若い菅田将暉、山崎賢人らも重要な役どころを演じており、見どころ満載です。
7-3.手紙のやり取りで人間ドラマが浮かび上がる「手紙」
犯罪加害者の親族の視点に立って、その心情の動向を丹念に追った作品。玉山鉄二が迫真の演技で迫ってきます!「手紙」のやり取りをする点では「ナミヤ雑貨店」と同じですが、こちらは時空を飛んだりはしません(笑)
8.まとめ
本作が、例え悩み傷つき、どん底にある時でも常に「他人のため」に行動する人たちの群像劇であったことが、作品を通してどこかしら感じられる「温かさ」「安心感」につながっていたのかなと感じました。
決して「古き良き昭和は良かった!」という懐古趣味一辺倒ではなく、今を生きる若者たちがそれぞれの道で自分自身を見つけた、という終わり方も良かったと思います。素直に見れば、心が浄化される泣ける作品です。
それではまた。
かるび
9.映画をより楽しむためのおすすめ関連映画・書籍など
ブルーレイ/DVD「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
3月23日にDVD/ブルーレイが発売となりますが、事前購入するなら、やっぱり豪華版がおすすめです。豪華版&早期予約特典を以下の通りまとめました!
小説原作「ナミヤ雑貨店の奇蹟」
上映時間の都合上、映画ではカットされた2つのエピソードや、登場人物たちの背景・人物描写がより詳細に描かれている他、敦也たちと相談者で何往復も出された手紙の生々しいやりとりが、(小説だけに)全文読めるため、映画とはまた違った緊張感や人間ドラマが味わえます。全世界で900万部売り上げただけあって、ストーリーの緻密さや組み立ては本当に上手。映画を見た後でも、別角度から何度でも楽しめます。
映画主題歌「REBORN」(山下達郎・門脇麦)
門脇麦が、劇中で2番までほぼフルコーラス近く歌い上げた「劇中歌バージョン」、エンディングでかかる山下達郎バージョンと、両方が収録されたマキシシングル。映画にあわせて山下達郎が描き下ろした歌詞も、物語の世界観にぴったりフィットしているため、聞き返すたびに感情移入できる素晴らしいテーマソングになりました。
東野圭吾の小説原作の作品は、まとめてU-NEXTで!

よく練り込まれた緻密なストーリーがベースにあるので、誰が監督を務めても一定の水準以上のクオリティにしっかり仕上がってくる東野圭吾作品。かなりの数が映画化・ドラマ化されていますが、まとめてチェックするのであればU-NEXTが良さそうです。東野圭吾原作映画では、U-NEXTが一番おすすめ。2018年3月現在、なんと大量11作品が「見放題」でチェックできます!
まずは、1つずつDVDを買うよりも、ビデオ・オンデマンドで時間とお金を節約してみてはいかがでしょうか。
★最初の31日間は無料!
加入後、最初の31日間は会員料金が無料です。見放題以外の有料作品も、初月付与される600ポイントを使えば、2本まで無料で見れます。さらに、毎月自動的に1200ポイント付与されるため、月額料金も、実質上業界最安クラスの800円なのですよね。国内最大120,000点の品揃えは映画ファンにはたまりません!
★100誌以上の雑誌も読み放題!
DVDだけでなく、雑誌まで読み放題サービスがついてくるんですね。僕も、映画以外にもサブカル、マンガ、エンタメ系の情報はU-NEXTで無料購読できる雑誌から仕入れています!毎月付与される1200ポイントで、電子書籍を購入することもできますよ!