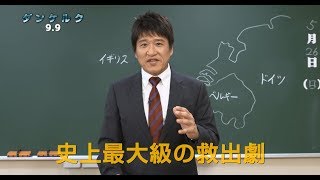かるび(@karub_imalive)です。
2017年の夏休みシーズンも、各地で子供向けに恐竜展が開催されています。中でも関東圏で大きく話題を呼んでいるのが、幕張で開催中の「ギガ恐竜展2017」と横浜の「横浜恐竜展2017」の2つです。
上記エントリの通り、実は、先週早速ギガ恐竜展2017に行ってきたばかりなのですが、展覧会マニアの血が騒ぐというか、どうしても、もう片方の「ヨコハマ恐竜展2017」を早く見たい!という衝動を抑えられなくなり、土日になる前に平日朝から行ってきました!
ギガ恐竜展は、幕張メッセの展示会場のデカさを最大限活用した、スケール感の大きい骨太な正統派展示でした。全長38メートルの超巨大恐竜骨格標本をはじめ、全部で200体を超える恐竜化石・模型が展示される圧巻の内容でした。
それに対して、ヨコハマ恐竜展は、恐竜ロボットが動く動く!スケール感や展示の物量こそギガ恐竜展に劣りますが、その分「動き」と「リアルさ」、そして手作り感のある展示で対抗しています!ギガ恐竜展とはまた一味違う魅力を、存分に楽しんできました!
早速ですが、当日の感想レポートを書いてみたいと思います。
- 1.「ヨコハマ恐竜展2017」とは
- 2.横浜恐竜展2017の3つのみどころ
- 3.その他、印象的だった展示内容について
- 4.グッズも充実!フィギュアやおもちゃが人気でした
- 5.混雑状況と所要時間目安・駐車場
- 6.まとめ
- 7.関連書籍・資料などの紹介
- 「ヨコハマ恐竜展2017」展覧会開催情報
1.「ヨコハマ恐竜展2017」とは

ここ数年、2012年、2014年、2015年と、2年に1回以上のぺースで、パシフィコ横浜を展示会場とする、夏季の横浜での恐竜展が定着してきています。(主催者は複数)年にもよりますが、大体夏休み期間中だけで20万人~30万人程度の入場者数を記録する大ヒットイベントで、横浜の夏の風物詩的な感じになってきていますね。
今回のヨコハマ恐竜展は、2015年の「ダイノワールド」以来2年ぶりとなりましたが、最新の研究成果に基づいて製作されたリアルな恐竜ロボットは一見の価値ありです!
会場マップはこんな感じ

引用:ヨコハマ恐竜展2017 ||~動く!ほえる!恐竜の森!~
入場すると、細かくパーテーションで区切られたスペースをジグザグに探検するように進んでいきます。オープンスペースで「どどーん」と展示が置かれたギガ恐竜展とはこのあたりは対照的。
展覧会本体の実質的な展示は、「恐竜の森」まで。それ以降は子供向けの簡易アトラクション「恐竜FUNランド」、ショップ、イベント・PRコーナー(軽食・体験イベント)と続いていきます。
音声ガイドもあります!

今回は、子供用と大人用にガイドが分かれていました。僕は大人用のガイドを選択。大人用は、手作り感満載の渋いガイドでした。音声がこもっていて、なんかコストダウンしましたって感じ(笑)
解説内容は特に問題ありませんが、チープな感じが全面に出ているのは残念でした。あえて苦言を呈するなら、恐竜展らしく、もう少しエンタメ色を強くして、親しみやすい感じにしたほうがいいんじゃないでしょうか?これは改善の余地ありです。
写真は撮り放題!
音声ガイドは今ひとつでしたが、その反面、写真撮影がオールOKなのは素晴らしい!受付でお姉さんに聞いた所、どんどんSNSにアップして下さい!ということでした。やっぱり恐竜展はそうでないと!僕も見終わってスマホをチェックしたら、300枚ほど写真撮ってました(笑)
また、記念写真コーナーもあります。それ以外のポイントでも、みんな子供と思い出の写真を撮りまくっていました。
▼恐竜と撮れる!記念写真コーナー
子供に最大限配慮した展示内容
恐竜展での主役はなんと言っても子供です。展覧会では、子供が最大限楽しめるよう、様々な配慮がされていたのは嬉しいところ。例えば、今回の恐竜展では「ベビーカーのまま入場してOK」ということ。ベビーカー置き場もありますが、そのまま入っていけるのはうれしいですね。
▼ベビーカー・車椅子での入場OK!
さらに、各展示の解説パネルも、子供向けにわかりやすくきちんとルビが振られています。小学校低学年から、自分で読んで自分で学べるようになっている配慮も、親としては嬉しいところでした。
▼解説パネルには漢字のよみがなを完備!
2.横浜恐竜展2017の3つのみどころ
見どころ1:大量17体のリアルなロボットが動く「恐竜の森」

ヨコハマ恐竜展のハイライトは、なんと言っても、展示後半にあるジャングルを模した「恐竜の森」コーナー。精巧にできた13種類17体の恐竜ロボットが、声を出して動きます!
▼沢山の「動く」恐竜たち!
これが結構リアルにできていて、小学生以下の小さい子供にはかなりのインパクトがあったようです!怖くてあちらこちらで泣き出してしまってました(笑)僕もいくつか撮って来ましたので、Youtubeにアップしてみました。(それぞれ30秒程度ですので、もしお時間があれば!)
どうでしょうか?派手に動くわけじゃないですけど、恐竜の唸り声などもちゃんと入っているので、迫力がありますね?!そして、結構子供が泣いているのがおわかりかと思います。小学生以下のお子さんを連れて行く際は、ある程度覚悟して下さい(笑)
見どころ2:初めての試み?つば吐き恐竜「ディロフォサウルス」がお目見え!

そして、「恐竜の森」コーナーで一番面白かったのは、つば吐き恐竜「ディロフォサウルス」です。映画「ジュラシック・パーク」では、毒のある唾液を吐いて敵を仕留める肉食恐竜でしたが、これがそのままロボットになって動いているんです!
ヨコハマ恐竜展2017では、このディロフォサウルスが、動きながら通路に向かって一定の時間間隔で口から水鉄砲のように水を吐いてきます!(映画と違って、もちろんただの水ですからご安心を)
今日もいっぱい元気に唾吐いてます。
— ヨコハマ恐竜展2017 (@yokohamakyoryu) 2017年7月17日
ご来場の際は、ご注意ください。 pic.twitter.com/9D0DLHtamM
このつば吐き恐竜「ディロフォサウルス」の直前には、こんな看板もありますので、いきなり不意打ちでずぶ濡れになるということはありません(笑)
で、どこから吐いているんだろう?と思って見てみると、口の中に鉄製のホースみたいなものが埋め込まれているんですよね。ここから水を吐いているようです。

ただ、実際に「ディロフォサウルス」がつばを吐く恐竜だったのか?という検証は特にありませんでした。フィクションの世界を再現した純粋なエンタテインメントとして楽しんでほしい、ということなのでしょうね。
見どころ3:出口を出てからが本番?遊べるアトラクション「恐竜FUNランド」!
今回の展覧会は、展示が終わってからも子どもたちが遊べるスペースが沢山用意されています。題して「恐竜FUNランド」。会場地図で見ると、場所的にはこのあたりです。

このコーナーでは、「宝さがし」「恐竜迷路」「恐竜発掘ゲーム」など、有料・無料合わせて6種類の簡易アトラクションが用意されており、子供を遊ばせるにはぴったりのコンテンツでした。
ちなみに、6種類あるうちの4つは有料コンテンツとなります。専用のチケット売り場で、1回=400円のチケットを購入して、チケットと引き換えに入場が可能となります。
▼有料コンテンツはチケットを購入する必要がある
では、いくつかコンテンツを見てみましょう。まず、「対決ディノニクス」。いわゆる的当てゲームですね。恐竜の体に描かれた「的」にボールを投げて、制限時間内に一定数のボールを当てることができれば、景品がもらえます!
▼有料アトラクション「対決ディノニクス」
つづいて、「恐竜迷路」。入り口から入って、立体迷路を出口に向かって進んでいくシンプルなゲームです。
▼「恐竜迷路」
そして、一番人気は「化石発掘広場」。こちらは無料で楽しむことができます。砂場に埋まっている化石を掘り出して見つけるゲームです。なお、「砂場」といっても、本物の砂ではなく、細かく裁断されたウッドチップのような材質の砂なので、服がドロドロに汚れることはありません(笑)
▼一番人気「化石発掘広場」
スポンサーリンク
3.その他、印象的だった展示内容について
3-1.ティラノサウルスの「動く」骨格展示が凄い迫力!

本展は、「恐竜の森」に設置された恐竜ロボットがメインですが、トリケラトプスやティラノサウルスなど、骨格標本の展示もしっかりしていました。中でも、この「動く骨格標本」は迫力満点!
ガイコツが大口を空けて咆哮する様子は、小さな子供をビビらせるのには十分すぎるほどで、この展示を見て一番泣きそうになる子供が多かったですね。
こちらも、動画に撮ってきました。約40秒ほどと短いので、もしよければ御覧ください!咆哮も恐竜の王者「ティラノサウルス」ぽくて良いですよね?!
3-2.触って学べるコーナーもあります
また、今回の展示では、ところどころ実際に化石(模型)を触って、その大きさや手触りを直接感じられるコーナーも設置されていました。「タッチステーション」という看板のある展示は、実際に触れて楽しむことができます!
▼触れる展示「タッチステーション」
こんな感じで置かれています。写真は、恐竜のたまごですね。
▼触って楽しめる!
3-3.恐竜研究の歴史
恐竜展で、意外と触れてくれないのが、恐竜発掘の歴史。「羽毛が生えていた」とか「恐竜は鳥類に進化した」など、最新の科学発見や知見は、どの展覧会でもしっかり示されますが、誰が最初に発見したのか?その歴史について、あまり展示を見ることがありません。 今回の「ヨコハマ恐竜展」では、地味ですが一番最初のコーナーでしっかり特集されていました。

展示によると、恐竜研究の歴史は、1822年にイギリスの医師、ギデオン・マンテル氏が、妻が見つけてきたイグアナに似た新種の化石に「イグアノドン」と名付けたところから始まりました。その後、自然学者オーウェンが一連の巨大爬虫類の化石群を1845年に「DINOSAURIA」と名付けて恐竜研究が本格化していったそうです。
▼1800年代の恐竜研究資料(複製)
スポンサーリンク
4.グッズも充実!フィギュアやおもちゃが人気でした
恐竜展の最後のお楽しみは、やっぱりおみやげですね。ヨコハマ恐竜展2017でも、沢山のグッズが並べられていました。目立ったところを紹介してみたいと思います。
▼お菓子「伝説の恐竜たまご」
「恐竜のたまご」は職場や親戚へのお土産の定番ですね。
▼自由研究に最適!子供向け書籍コーナーも!
今回の展覧会は、いわゆる「公式図録」の販売はありません。でも、子供向けにイラスト満載の恐竜本がたくさん売られていました。
▼やっぱり大人気!恐竜フィギュア!
そして、一番人気はやっぱりフィギュアですね!ワゴンに無造作に積まれたものから、棚に収まっているもの、ビニール製、ゴム製など様々な種類や大きさのものがが用意されていました。
▼ヨコハマ恐竜展にも!スーパーボールガチャ!
ボールの中に、恐竜が封じ込められたスーパーボールのガチャマシーン。物販コーナーの真ん中にどどーんと鎮座しています。
▼恐竜プラモデル!
タミヤから、恐竜のプラモデルも沢山出ていました。箱の大きさに比べて値段がリーズナブルなのも嬉しい所。小学生の時、よく作ったな~。
▼意外に人気?フィギュアつかみどり
そして、意外と人気を博していたのが、手のひらサイズの小さな恐竜フィギュアをつかみどりできるサービス。箱の丸い穴の中へ手を突っ込んで、1回500円でつかめるだけ持って帰れます。見ていると、これがうまく出来ていて、掴みすぎると手が膨らんで箱から手が抜けなくなるんですよね(笑)
▼恐竜ガチャマシーンもこんなに!
出ました定番のガチャマシーン!全部で20種類用意されていますので、心ゆくまで楽しめますね!
5.混雑状況と所要時間目安・駐車場

僕が行ってきたのは、7月20日(木)朝10時30分~12時。平日なので空いていましたが、夏休みに入って、休日やお盆、会期末などは普通に混雑しそうです。今のところ入場制限がかかった実績はありませんが、当日行く前にTwitterの公式アカウントを一応フォロー&チェックしておいたほうがいいかもしれません。
初日から大盛況です!
— ヨコハマ恐竜展2017 (@yokohamakyoryu) 2017年7月15日
たくさんのお客さまにお越しいただいてます! pic.twitter.com/xhvBOpMRlr
また、駐車場については、パシフィコ横浜の地下駐車場があるにはありますが、休日に行くのであればマイカーでの来場はオススメしません。平日でもほぼ満車近くまで普通に埋まっていますので、休日は確実に駐車場への入場待ち行列ができるはずです。また、駐車料金も決して安くありませんのでご注意!
所要時間としては、60分~90分あれば十分に見て回れると思います。今回のヨコハマ恐竜展は、ロボット恐竜の動きから、体感的に学ぶのが主となりますので、それほど情報量が多いわけではありません。
6.まとめ
展示規模や、コンテンツ量などは、正直なところ、同時期に開催されている幕張メッセの「ギガ恐竜展2017」の方が格段に上ではあります。しかし、その分ヨコハマ恐竜展2017では、17体もの動く恐竜ロボットによって、よりリアルに恐竜を体感できるのが最大の特徴でした。大人はともかく、子供にはインパクト絶大だと思います!
また、後半部分のミニアトラクションや、PRコーナーなど、アマチュアっぽい感じはするんですが、縁日のような手作り感・地元密着感が感じられたのは面白かったです。子供との思い出づくりや、自由研究の取っ掛かりとして非常に良い展示だったのではないでしょうか?
終わってからも、海辺を散策したり、関連コンテンツとの相互割引もありますので、横浜観光に組み込んでみてもいいですね!
それではまた。
かるび
7.関連書籍・資料などの紹介
小学生Youtuberの動画が素晴らしい!
Youtubeにアップされている動画で、(おそらく親御さんがまとめていらっしゃるのだと思いますが)MIKUちゃんという小学生が会場内をレポートして回っている「MIKUTV」がわかりやすくて素晴らしいです。是非チェックしてみて下さい!
ベストセラー!ナショナル・ジオグラフィック「恐竜がいた地球」
いわば「恐竜入門編」でもあるヨコハマ恐竜展を見た後、大人が次に恐竜について本格的な教養を求めようと思ったら、こちらのムック本がオススメ。恐竜についての最新の科学研究成果がわかりやすいイラスト・写真・図表でまとまった本格派ムック。Amazonで売れ行きNo.1となっています!(2017/7/17現在)
映画でも味わおう!「ジュラシック・パーク」シリーズ!
恐竜展を見終わった後って、無性に恐竜コンテンツをもう少し見たいと思ったことってありませんか?僕も、思わず自宅に帰ってから「そうだ!DVDでまとめ買いしよう!」と思い立ち、「ジュラシック・パーク」シリーズが全部まとまったDVDをポチってしまいました!あの、つば吐き恐竜も出ていますよ!
「ヨコハマ恐竜展2017」展覧会開催情報
◯美術館・所在地
パシフィコ横浜 展示ホールA
〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1
◯最寄り駅
東急みなとみらい駅から徒歩5分(地下道直結)
JR桜木町駅から徒歩10分
◯会期・開館時間・休館日
2017年7月15日~9月3日(会期中無休)
10時00分~16時30分(入場は30分前まで)
◯公式HP
http://yokohamakyoryu.jp/
◯Twitter
https://twitter.com/yokohamakyoryu